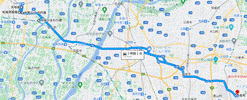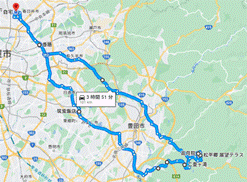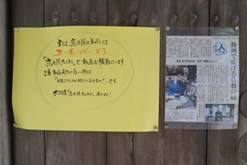|
トコトコ中国バスの旅 |
|
|
|
|
|
|||
【旅日記】
|
2022.8.7(日)
やっぱり日本は素晴らしい |
|
|
ひまわりの咲く季節になった。 満を持して、いざ西へ。 |
|
|
9:23 大垣ひまわり畑に到着。 協力金200円を納め、畑の中へ。 木曽川を越えた辺りからだったろうか? 脚立を積んだピンクナンバーのカブと、抜きつ抜かれつが続いた。 もしやと思ったら、案の定目的地は同じだった。 |
|
|
大垣市の広報ページによると、約3.2ヘクタールに14万本植えられている。 見頃は8月上旬〜下旬。夜はライトアップもあり。 開花は播種後60日前後だそうだ。 |
|
|
見事に咲いていて良かった。 |
|
|
北京でもこんな風景を期待し、毎年この時期に四海花海へ行っていた。 しかし、一面に咲く姿を見たのは一度きりでガッカリが続いたなぁ。 |
|
|
新幹線から眺めるのも良さそう。 下りなら、岐阜羽島を越えたら進行方向右側を注目! |
|
|
暑い中、ミツバチ達がせっせと働いていた。 |
|
|
10:02 水の城「大垣城」へ到着。 予想外。真っ平らな場所、しかも商店街の奥に建っていた。 三重だった総堀が、水門川や用水路として残る以外戦後に埋められ、計画性の無い開発により道路や天守より高い建物ができ、大垣駅から見えなくなった。2005年、昔の大垣城を復活しようと市が「大垣城郭整備ドリーム構想」を立ち上げたが、度々検討委員会を開催するも計画は具体化しておらず。今となってはなぁ。 |
|
|
大垣駅通りの商店街には、紅白の横断幕に屋台がズラリ。 この土日夜、ここで水都祭りの盆踊りが行われていたからだ。 |
|
|
立派な東門は、往時の柳口御門を移築したもの。 本来はここに門は有らず。そうだわな〜、天守の足元だもんな〜。 門前には昭和レトロな建物が並ぶ。 |
|
|
手前はビリヤードのエグロ会館。 軒先の「玉突」掛行燈が光る。 |
|
|
大垣城は美濃守護・土岐一族の宮川吉左衛門尉安定により、天文4年(1535年)に創建されたと伝わる。 関ケ原の戦いでは、西軍・石田三成の本拠地となった。 その後、戸田氏が十万石の城主となり明治まで太平の世が続いた。 明治13年(1880年)、本丸敷地への中学校設置の危機を乗り越え、昭和11年(1936年)、国宝に指定されが、昭和20年(1945年)7月29日に戦災で焼失。 う〜ん、残念。 昭和34年(1959年)4月、戦前の大垣城をモデルに復元された郡上八幡城をモデルに4層4階の天守を再建した。 |
|
|
北側の水之手門跡。 水堀に囲まれた本丸から船で内堀に降りることができたとされている。 戦後の開発により多くの遺構は失われ、石灰岩でできた本丸の石垣と外堀だった水門川が残るのみ。 移築されたものも多く、市内の民家に本丸乾門、市内の天理教教会に清水御門が残る。 どこの門か分からないが市内の民家に、鵜沼宿にある鉄門も大垣城から各務原の野口城に移築された物。 |
|
|
水門川に沿ってミニ奥の細道を西へ進むと、龍の口橋の袂に石碑が2つ建っていた。 |
|
|
大きな石碑は、「大垣高等女学校発祥の地」。 小さな方は、「被爆地跡」。 昨日は広島原爆の日。TVで平和祈念式典を見て黙祷した。導かれたのかな。 昭和20年7月24日午前8時、B29により模擬原子爆弾「パンプキン」が投下され多くの命が奪われた。 大垣市には、戦前より揖斐川電気、鐘淵紡績大垣工場、住友通信工業大垣製造所等の工場が多く、計6回空襲を受けた。 |
|
|
水門川は、春には「たらい舟」に揺られて桜の花見ができるようだ。 |
|
|
大垣市役所のモニュメント前で地図を確認。 |
|
|
10:32美濃路の西総門跡へ到着。 京都方面にあることから「京口門」とも呼ばれ、明け六つに開かれ、暮れ六つに閉じられた。 ここに門を設け総堀に橋を架けることで、有事の際に外部との交通を遮断するなどの防御が図られた。 |
|
|
橋を渡ると、「飛騨・美濃さくら三十三選の地 奥の細道むすひの地」の碑。 何故ここが結び地なのか、後で分かった。 |
|
|
水門川に掛かる貝殻橋の袂には、「右京みち 左江戸道」と彫られた船町道標が建つ。 高さ約2mの円柱で、文政年間(1818-1830年)に設置された。 正対すると左右が逆でややこしい道標だと思ったら、これも移築されて来たものだった。 |
|
|
四季の広場から、水門川遊歩道「四季の路」へ下りてみた。 四季の路は、水門川沿いにつくられた全長2.2kmの遊歩道。 大垣駅東の愛宕神社から、大垣駅通りを横切り、八幡神社前を通って、船町の奥の細道むすびの地に至る。 「奥の細道」全行程2,400kmを、この2.2kmに見立て、松尾芭蕉が詠んだ代表的な20句の句碑と句が詠まれた土地の説明版を設置。「矢立初めの句碑」、「蛤塚」とあわせた22句で芭蕉の足跡を辿る「ミニ奥の細道」。 |
|
|
滝のトンネル。裏側へも行ける。 |
|
|
7月に入り度々エンジン不調を起こした愛車。とうとう寝覚め無くなり、炎天下に小牧山から自宅まで9kmの道程を押す羽目になった。 何度かキャブを清掃。ジェットやニードルは新品に交換。何とか息を吹き返したが、アクセルを開くとストール。 後はポイント。交換はおろか、調整も工具が無いので出来ない。エンジンが掛かっているうちに、騙し騙し走ってバイク屋へ。 一週間入院し、ポイントとプラグキャップ交換、キャブをしっかり清掃して貰い復活!これで安心して走れる。 ポイントは錆びや摩耗で、掛かっていたのが不思議なぐらいだったそうだ。それを思うと、9kmならラッキー。 |
|
|
奥の細道むすびの地記念館 2008年、大垣市制90周年を記念し、芭蕉と親交のあった俳人・谷木因の邸跡に建てられた。 |
|
|
「鉄心門」と呼ばれる立派な門は、大垣藩家老・小原鉄心邸宅の裏門だった。 この門もあちこち転々とし、平成24年(2012年)にこの場所へ移築された。 茅葺の煎茶室は小原鉄心の別荘「無何有荘」の大醒榭。鉄心門と共に移築された。 和風に中国風意匠を取り入れた設計で、茶室・湯殿・水屋・厠の4室で構成されている。 南側の衝立には、江戸時代には珍しい「ギヤマン」と呼ばれた色ガラスが嵌め込まれている。 |
|
|
元禄2年(1689年)秋、芭蕉は「蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ」と詠み、この船町港から桑名へ舟で下り、約5ヶ月に亘る『奥の細道』の旅を終えた。 |
|
|
芭蕉が初めて大垣を訪れたのは、『野ざらし紀行』の旅の途中、貞享元年(1684年)9月下旬のこと。 目的は、以前から親交があった船問屋の谷木因への訪問。 この時、木因宅に1ヶ月ほど滞在し、木因の仲立ちで大垣の俳人たちが新たな門人になった。 |
|
|
芭蕉が門人に宛てた手紙によれば、『奥の細道』の旅のむすびの地は、旅立つ前から大垣と決めていたことが伺えるらしい。 背景には、早くから自分の俳風を受け入れた親しい友人や門人達の存在があったとか。 なるほど、そう言う事だったか。 |
|
|
正面に見える市役所が無ければ、往時と変わらぬ風景かも。 |
|
|
天保11年(1840年)に建てられたとされる住吉燈台。 高さ8mの寄棟造りで、往時は最上部の四方に油紙障子を嵌め込み中央に燈火を入れた。 明治16年(1883年)には、大垣-桑名間に蒸気船が就航し活躍。 昭和期になると、鉄道等の陸上輸送網が発達し役目を終えた。 |
|
|
ゆっくり散策するのも良いだろう。 |
|
|
10:58 決めておいた中村屋へ到着。 開店2分前だったので列が出来ていた。 名古屋の店が撤退して以来。久し振り。何年になるだろうか? 11:00 「やっとる」の看板が表に出て開店。第1陣の最後でカウンター席をゲット。 |
|
|
オーダーは、当然中華そば大盛 910円。おにぎりは、数量限定のランチサービス。嬉しい! 懐かしい味。動物系と魚介系をブレンドしたWスープが堪らない!もちろん完食。 しかし、一口目のスープで感じたのは「スガキヤ」の味。侮れないなぁ。 帰路、BOOK-OFFに立ち寄り、欲しかった「珍妃の井戸」を110円でゲット。Monkeyは快調だし、言うこと無し。 |
|
|
2022.8.27(土)
酷い目にもあったが、良いルート設定だった |
|
|
徳川300 年の礎となった松平氏発祥の地、豊田市の松平郷から二畳ケ滝、奥殿陣屋のルートを設定。 昨夜、中ジョッキの生ビールを3杯飲んだ後で残務を片付けようとPCへ向っていたが、思う様に進まず頭が痛くなり、この所ハマっている“蒼穹の昴シリーズ”の読破もそこそこに眠った。 この時点では余り出掛ける気がしていなかったが、朝、改めてPCへ向うと、アッと言う間に解決策を発見! これで気分が良くなり出掛けることにした。 |
|
|
9:34 松平城跡へ到着。トイレ休憩。 東海環状自動車道・豊田松平IC前の長い坂を下り切り、巴川に掛かる松平橋をR301は急な上り坂になる。 案の定、だんだんスピードが落ちて行く。あ〜、トンネルが迫って来る〜。 幸い後続車が無くて良かった。特に豊田市は安全な距離を取らず追い越す乱暴な車が多く怖い。 |
|
|
八幡神社松平東照宮 始めは、八幡宮と称して松平家の屋敷神だったが、元和5 年
(1619 年)家康を合祀、昭和40 年(1965 年)親氏公を合祀した。 松平太郎左衛門家は、大正初期までこの地に居住した。 松平郷の開拓領主は、後宇多天皇(在位1274 - 87年)に仕えた公家の在原信盛と言う。 入郷は弘安年間(1278 - 87年)。この松平東照宮境内に本屋敷を構えたと伝えられている。 |
|
|
水濠や石垣は、松平太郎左衛門家九代尚栄によって関ケ原の合戦のあと築かれたもの。 少し前に水を抜いたが、お宝は出て来なかったとか。 |
|
|
本殿の天井には、松平で見られる季節の草花が108枚の漆絵に描かれている。 2015年の徳川家康公400年祭メモリアル事業として、安藤則義氏が2年の月日をかけて描いたもの。 |
|
|
神殿もご立派! |
|
|
在原信盛が掘ったと言われ、松平家は代々この井戸の水を産湯に用いた。 岡崎城主 松平広忠の子、竹千代(後の家康)が誕生した際(1542年)、この水を竹筒に入れ早馬で届けたと言われている。 |
|
|
松平東照宮の先の分かれ道を、左へ行くと松平郷展望テラス。右へ行くと高月院。 先ずは高月院へ向う。 |
|
|
高月院 1367年、足助次郎重宗の子、重政(寛立上人)が松平郷主・在原信重の援護を受け「寂静寺」として建立。 1377年、親氏が本尊阿弥陀仏をはじめ、堂・塔のすべてを寄進してから「高月院」と改め、松平氏の菩提寺となった。 その後、徳川家康によって寺領100 石が与えられ、明治維新まで時の将軍家から厚い保護を受けていた。 山門や本堂は、徳川家光が1641年に創建したものと言われている。 |
|
|
本堂の左手奥に三つ葉葵紋の石扉の松平氏墓所がある。 松平親氏、二代泰親、四代親忠夫夫人の宝篋印塔三基が祀られている。 |
|
|
ここの和尚はYouTuber 。 お坊さんにはピッタリだなぁ。 |
|
|
9:54松平郷展望テラスへ到着。 松平東照宮まで戻り、標高310mまでゆっくり山道を上って行く。 右側の道標に気を取られ通り過ぎてしまった。 |
|
|
あった、あった。が、立派な名前とは裏腹に、小さいなぁ。 売店どころか自販機も水道も無いので、歩いて来る場合は水分の準備が必要。 |
|
|
良い眺め! 豊田市内が見渡せた。 クリアなら、名古屋駅周辺の高層ビル、東山スカイタワー、名港トリトンはおろか、伊勢湾や三河湾対岸の鈴鹿山脈、養老山脈まで眺望できるそうだ。 |
|
|
10:08 R301の根引峠を通過。ここからの眺めも素晴らしい! 相変わらず険しい峠だが、随分道幅が広がり走り易くなった様な気がする。 大きなバイクなら、さぞ気持ちが良い事だろう。 |
|
|
10:21 県道338号線を郡界川沿いに進むと、突然、川底にゴツゴツとした大きな岩が現れた。 二畳ケ滝へ着いたようだ。 |
|
|
高さ約30m、幅7m、岩盤が重なり激流が二層になって落下するのが名前の由来と言われている。 ここには大蛇が住むといわれる穴があり、「目撃した人は蛇の毒気で熱病になる」、「滝壷には竜神が住み、滝に触れると祟りがある」など多くの伝承が残されている。 大雨の後は水量が増え激流となり、迫力のある流れを見ることができるとか。 |
|
|
これは素晴らしい! 蛇行する姿も見たかった。ドローンがあればな〜。 中国なら、間違いなく「双頭龍瀑布」と命名。 大雨の後はさぞ暴れることだろう。 |
|
|
ゴミなど一つも無い素晴らしい所だったが、42年前は違っていたようだ。 写生に来た小学生が話し合い、願い、掃除を続けて来た。泣ける。 |
|
|
県道338号線を西へ向い、岡崎市に入ると小高い山の上に立派な神社を発見。その名は御鍬神社。 お鍬さま信仰は伊勢神宮の御田植初め神事より出たもので、その時に使う忌鍬諸国に祀り、農の豊穣を祈ったもの。 故に、辺り一帯が見渡せるこの場所を選んだ訳か。 |
|
|
10:55 奥殿陣屋に到着。 ここでポツポツ雨が降って来た。 |
|
|
‘06年放送のNHK連続テレビ小説「純情きらり」のロケ地。 広州で見ていた筈だが、思い出せない。 |
|
|
徳川秀忠に仕え、大坂の陣の戦功により3千石を与えられた松平真次が、大給(豊田市)に陣屋を構えたことから奥殿松平家が始まった。 第2代乗次のとき1万6千石の大名となり、宝永4年(1707年)に奥殿に陣屋が完成したため第4代乗真が移った。 以後、文久3年(1863年)に信濃国佐久郡田野口村(長野県佐久市)に龍岡城を築城して藩庁を移すまで奥殿藩の中心となった。 藩庁の移転をおこなった最後の藩主松平乗謨(明治維新後に大給恒と改名)は、博愛社(日本赤十字社の前身)の設立に尽力した人物。 |
|
|
当時は御殿・役所・書院・学問所・厩・馬場などがあったが、廃藩置県後にそれらは移築や取り壊しが行われ、陣屋の跡地はほぼ田畑となった。 そこに、岡崎市桑原町にある曹洞宗の寺院・龍渓院の庫裏になっていた書院が移築され、昭和60年(1985年)にオープン。 と言う事で、立派な建物だが少々残念。 |
|
|
書院の中は、抹茶を中心に和風飲料が提供される喫茶店。 庭を眺めながら一息つくのも良いか。 |
|
|
奥の村積山には歴代藩主廟所などがある。 鬱蒼と木の茂る山に入ると、陣屋の境を示すと共に防御と災害対策の役目を兼ねる土塁があった。 陣屋の南と東に約200m築かれていたと言うから、広い! 暗くなったら、恐ろしくて立ち入れない。 |
|
|
神社も何だか、、、 |
|
|
立派な墓標が並ぶ。 |
|
|
それが山の上にも続く。 |
|
|
11:27 トヨタ本社前を通過。雨こそ降っていないが、この辺りの道路は水浸し。 何十年も前、小学校の社会見学で訪れた時に左の建物前の階段で撮影した集合写真がある。 つい昨日の事の様だが、、、 ここでR248を南進し、昭和Likeな鈴屋食堂で昼食の予定だったが雨が心配で変更。 先ずは、先日同僚との会話で盛り上がった東郷町の筑紫飯店へ向った。 |
|
|
11:59跳ね飛ばされないようR153を慎重に走り到着。雨の心配も無さそうなので、心置きなく店の中へ。 平成の改装で綺麗になったが、創業は昭和54年。もう老舗だ。 以前は職場が近かった事もあり、良く来ていた。少し前に久し振りに寄ったら、担担麺の味が変わっていて少々残念だった。その時に、台湾麺の味が気になり今回はその確認。 |
|
|
麺4種類×飯3種類の1,000円土日ランチの中から、台湾麺と炒飯をチョイス。飯は通常より少ないとの事なので、大盛100円をプラス。 出て来た超大盛炒飯を見て吃驚。これなら大盛にしなくても良かったんじゃないか。 肝心の味は? メニューには唐辛子マークがMax.の4つ付いていたが、辛さがマイルドになっていた。 炒飯も、ちょっと味が違うし、昔はもっとパラパラだったような気がする。 何年か前、初代が引退し弟子に暖簾を引き継いだ。その後、火事があり立ち直って頑張っているのは良いが、決して不味くはないものの満足できず。ランチには無い、真打の豚細切り焼きそばはどうだろう? |
|
|
13:04 最後に、今週食べログで発見した守山区のシルクロード料理・香膳を調査。 入口に「準備中」の札がぶら下がっていた。食べログに「前日までに電話予約」と出ていたのは、こんな事がチョイチョイあるからだろう。予約して行ってみよう。 交通量の多い国道を走り続け疲れた。おまけに、R248では前に割り込んで来た車に水飛沫を浴びせられた。 そんなこともあったが、二畳ケ滝には行って良かった。 |
|