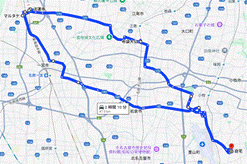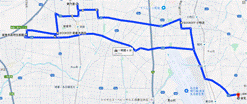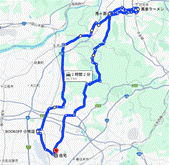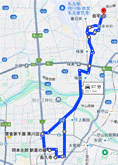|
トコトコ中国バスの旅 |
|
|
|
|
|
|||
▼My Collection -
Monkey - 訪問地 -
美食
【旅日記】
|
2024.9.7(土)
久々のツーリングで準備が、、、カメラを忘れ面倒なことになった |
|
|
久し振りのツーリング。振り返ると3ヵ月振り。 今年の夏は殺人的な暑さが続き、人車ともに大事を取って来た。 朝は涼しくなって来たので再開を決めた。 目的地は、以前から気になっていた一宮市木曽川資料館。 周辺の飲食店を調べると、良い店が見つかった。その他の訪問地とルートを決め、いざ出発! と、勢い良く出発したが、最初の目的地でカメラを忘れたことに気付いた。仕方ない、今回はスマホで行こう。 |
|
|
9:44 江南市の布袋大仏へ到着。 個人建造のコンクリート巨大仏像。奈良の大仏より3m高い18m。 本尊は御嶽薬師尊。誓願すると病気を除き、不具を癒し、悟りへの道に到達する? 県の公式観光ガイドに「・・・大仏がサングラスをかけている・・・」とある。 お〜、確かに。踏切の信号機がバッチリ両目に!これは面白い。 |
|
|
10:19 一宮市の黒田城跡へ到着。 戦国時代からこの地にあった城で七代の城主の記録が残る。 中でも土佐20万石の大名に出世した山内一豊はこの城で生まれたと言われている。 岩倉生誕説もあるので、良く有るご当地神話かも。 JR東海道本線沿い、黒田小学校北東側の一角に城門が再現されている。 |
|
|
大正6年(1917年)に愛知県が建てた「黒田城址」碑の裏面に「山内一豊は13歳でこの城を離れた」の銘記。 一豊顕彰会が設置した偉人を讃えた「一豊立志像」もある。 町に幟が並んでいた。何かと思ったら、9月15日に「一豊まつり」が計画されていた。 41回目になり、戦国時代パレードもある本格的な祭り。興味あり。 |
|
|
10:28一宮市木曽川資料館へ到着。 風格のある建物は、大正13年(1924年)に竣工した旧木曽川町会議事堂。国指定重要文化財。 山内一豊を中心に、浅野長政、兼松正吉、奥村永福など一宮市ゆかりの戦国武将、史跡などを紹介。 |
|
|
中では、ジジババが大音量で盆踊りの練習?中。 ショーケースには、郡上おどりの師範認定証がズラリ。 ゆっくり見たかったのでガッカリ。 そして、民具や農具はどこに? |
|
|
10:43 法蓮寺へ到着。 法蓮寺本堂北には、黒田城主だった一豊の父・山内但馬守盛豊と兄・十郎の墓がある。 兄は弘治3年(1557年)に黒田城で夜襲にあい死亡。 父は永禄2年(1559年)に岩倉城落城時に死亡したとされる。 |
|
|
ここにも「山内一豊出生地」の碑。 |
|
|
本堂北の山内但馬守盛豊と、その長男である十郎の墓。 向かって右側が、父盛豊の墓。墓石の施主は不明だが江戸時代中期の建立。 弘治3年(1557)城が夜襲され、十郎は戦死、盛豊は重傷、次男一豊はじめ一家は岩倉城へ逃れた。 盛豊は、浮野合戦で戦死するが、後に父子ともにここに葬られた。 |
|
|
「山内但馬守盛豊」と、しっかり読み取れた。 |
|
|
10:57ラーメン・ギョーザの店「マルタケ」へ到着。 名鉄新木曽川駅から東へ約300m。県道175号線に面しており分かり易い。駐車場も多くて良い。 何にもまして、この昭和感が堪らない。勿論、店内も同じ。創業は昭和40年代? 開店前、若者2人が外で待っている所に、いかにも常連らしき年配の家族が「入れるだろう」とズカズカ入店。 |
|
|
私を含め、最初の客からオーダーを取った後で、オッチャンが「さあ始めるよ」と声を掛け看板をドアへ。 おおらかでホッとする。 丼を並べてから、何度もオーダー伝票を読み込むオッチャン。その姿を見て、他人事とは思えず。 炒飯を炒めるオッチャンの右手には、丸いお玉ではなく平べったいコテ。 殆どの客がオーダーしていたので相当な様子。 看板の餃子はオバちゃんが焼いていた。そっちも美味そうだった。 |
|
|
オーダーはチャーシューメン。えっ、そんなのメニューに無いんですけど。 ラーメン大盛750円と決めていたが、隣の若者たちが頼んでいたので釣られてしまった。 他にも、「硬め」やら「濃い目」やら、裏メニューのオーダーが続々。中々面白い。次は炒飯も食べるぞ〜! お〜、来た〜。チャーシューで埋め尽くされ麺が見えない! 厚みは上州家に遠く及ばないが、柔らかくて弾力があり味もバッチリのチャーシューは絶品。納得の1,000円。 スープは屋台を思わせる懐かしい味で美味い!硬めの麺は賛同。味濃い目は相当血圧が上がりそう。 |
|
|
2024.9.14(土)
山内一豊生誕地の流れで岩倉へ |
|
|
9月も半ばになったが、まだ毎日体温に近い暑さが続いている。 割り合い涼しくなった朝方出掛けようと思うが、昼食がメインとなりつつある今、遠出は帰りが地獄。 よって、近場で目的地を決めることになる。いつまで続けることになるのか? 今回は、先週の山内一豊生誕地の流れで岩倉を目的地に決めた。 |
|
|
10:11 岩倉市史跡公園へ到着。尾張平野の弥生文化を知る上で極めて重要な遺跡。 昭和年22(1947年)、大地町野合地内の畑から土器の壷が出土。 弥生中期前半に属するもので、尾張地方北部を中心に分布することが判明。 以後、この土器群は「大地式土器」と称されるようになった。 |
|
|
昭和26年(1951年)、名古屋大学考古学研究室の指導で、壷が出土した一帯を発掘調査。 縄文時代後期や弥生時代中期・後期の土器に混じって、東西約7m、南北約4mの竪穴住居跡が見つかった。 昭和29年(1954年)、大地遺跡として愛知県指定史跡に指定された。 これらの歴史的な発見から、大地遺跡とその周辺の土地を岩倉市が取得。 平成8年(1996年)、市民の歴史学習の場としてこの史跡公園が整備された。 |
|
|
想像復元した竪穴住。 骨組みがしっかりしており、大地震でも倒れることは無さそう。 入口は低く出入りは難儀だが、中は広々。外気温は既に32-3℃、流石に涼しさは感じなかった。 |
|
|
名鉄犬山線・岩倉駅から北へ1kmほど行った本町北廻間のY字路にあった道標。 享和2年(1802年)、「右
あざい道、左 一ノみや道」 |
|
|
東町にあった農家の母屋を市役所東側から再移築した烏居建民家。 「鳥居建て」とは、主柱が二本あり、梁がこの柱にかかり、その下にツナギが1本横渡しになっている形が神社の鳥居に似ていることによる。 実際に使用されていた当時は、藁葺で軒は瓦葺の普通の農家だった。江戸時代に建築された建物。 |
|
|
内部は建築当初のままで、ほとんど手を加えた跡は無い。 家屋の構造から、室町時代における農家の形式を残している貴重なもの。 竈と囲炉裏、これで十分だよなぁ。 茶会や社会見学なら良いが、小学生の遠足で連れて来られるのは少々可哀想。 |
|
|
10:27 岩倉市自然生態園へ到着。 「自然との共生」を目指し、固有のビオトープとして、小川、池、湿地などを隣接する津島神社の森と一体のものとして整備。 ビオトープって? ドイツ語で、直訳は「生命の場所」。湿地、雑木林、池などに存在する固有の動植物群を保持する空間。 動物が自力で生活し、その「種」の永続的な持続が可能な場所や環境を言うそうである。 |
|
|
門柱の間を通り抜け、森の中へ。 樹齢200年をこえるシラカシの木を始め100種類におよぶ草木が生育する歴史のある森。 形成には250年以上の歳月がかかったと考えられている。市内でも有数の貴重な自然。 正面に赤い鳥居が見えた。津島神社。 あれ、行き止まりなのね。 |
|
|
戻って木製の八つ橋を渡る。 ここには、木や草など古くからこの地域にあった植物類が植えられている。 こうして、生物が住みやすい環境を整え、つい最近までどこにでもあたりまえに存在していた、数多くの生き物を呼び戻そうとしている。 |
|
|
野鳥、昆虫、小魚、ザリガニ、生態系はどこまで復活したのだろう? 子供達の虫篭は賑わうだろうか。 |
|
|
草屋根昆虫館。あ〜、廃墟じゃ。 しかも、蚊が多くてかなわん。 こうもりタワーに登ってみたいが、ギブアップ。 |
|
|
11:00 史跡公園の道標があった場所に近い東乃里に到着。 前々から目星を付けていた御食事処。漸く来れた。 Just開店時間だが、大駐車場は6割方埋まっていた。 少々ビビりながら入店。あ〜良かった、カウンターは空いていた。 |
|
|
オーダーは、予め決めていた「もも唐あげ定食」 850円!ご飯は、サービスの“多め”。嬉しいね〜。 アッと言う間に運ばれて来た。ちょっと心配したが、唐揚げは柔らかくジューシー。美味かった! それもその筈、人気No.1で厨房ではベテランのオッチャンが次から次へと調理していた。 良い店に出会えた。しかも、日曜日もこの値段でランチが食べられる。が、壁に目をやり残念なお知らせ発見。 何と、10/31に45年の歴史に幕を下ろすそうだ。それまでにもう一度、次はネギマフライ定食850円だ! |
|
|
2024.9.21(土)
鬼退治に向かう桃太郎たちの目的地 |
|
|
地図を眺めていて鬼ヶ島を発見! 場所は岐阜県可児市の可児川。2km下流で木曽川に流れ込む。 そこから6km下流に桃太郎神社がある。 これは行ってみるしかない。 いざ桃太郎伝説の旅へ。 |
|
|
10:47 鬼ヶ島へ到着。 看板によると、森になった中洲が鬼ヶ島。 ここから桃太郎神社までは、桃太郎伝説にちなむ地名が其処彼処にある。 |
|
|
可児川に架かる戸走橋からより。 鬼たちが住む本拠地、鬼退治に向かう桃太郎たちの目的地としては小じんまりしている。 約2000万年にこの付近に存在した火山の噴火で発生した火砕流によってできた凝灰角礫岩の島。 かつて山賊の住処であったと推測されている。そんな事から伝説の地になったのだろう。 |
|
|
北側へ回ってみたが、上陸できず。残念! しかし、ここなら伝説の舟はいらず、渡河できそうだ。 |
|
|
11:22 満楽ラーメンへ到着。 ややっ!ガッツリ工事中。止めちゃった??店内の赤い看板に「ラーメン・・・」と見えるし、、、 いや、満楽ラーメンはその奥だった。 |
|
|
開店時間の少し前に店頭の看板が営業中に変わった。 入店し、愛車前のテーブルに着席。これは良い。安心安心。 目指すランチの看板を探すと、レジの横に掛けてあった。 種類は事前調査の通り、価格は7月情報から100円Up。もしかしたら、副菜によって変動? |
|
|
オーダーは、Cランチの担々麺 970円。 来た来た!真っ黒なラーメンに惹かれてココに決めた。その正体は黒ゴマ。たっぷり入っていて美味しい。 副菜は麻婆豆腐。こちらは、ストライクゾーンから少々外れていたが、日本なら普通に出て来る感じ。 1,000以内でこれが食べられるとは、可児市民が羨ましい。 もう一つ気になっていた満楽麺の正体も判明。こっちは白ゴマだった。常連にはこっちが人気だった。 |
|
|
2024.9.28(土)
名古屋で寺巡り |
|
|
今週は健康診断を受診。産業医からキツク指導を受け、減量を固く決意。 ヘルシーな昼食も条件に、目的地を「歓喜の鐘」に決定。 周辺を調べてみると、清洲城の裏門がみつかりルートが決まった。 |
|
|
10:15 名古屋市東区の長久寺へ到着。 慶長5年(1600年)尾張国清須城に移された松平忠吉が、旧領武蔵国忍城下で祈願所としていた寺を清須に移した。 10年後、清須越えの際に徳川義直が名古屋城へ入ると現在地へ移され、尾張徳川家の祈願所となると共に新義真言宗の学問所が設置された。 |
|
|
薬医門形式の立派な表門は、清洲城の裏門を移築したもの。 |
|
|
日本の女優第1号である川上貞奴が名古屋を去るに当たり、二葉御殿の仏間に祀っていた不動尊を、長久寺に寄進した。 寺の北側には、儒学者 細野要斎が明治11年(1878年)没するまで住んでいた。 細野要斎は、文化8年(1811年)生まれ。幼少より学問を好み、儒学、書道を修め、垂加神道の伝を受けた。 家を継ぎ、馬廻組・大番組として仕えるなか、学才を認められ藩校明倫堂の典籍の職を任じられた。 藩主徳川義宜の侍講。明倫堂の督学に進んだ。晩年は、「尾張名家誌」の編纂に力を注いだ。 |
|
|
本堂前庭に、市の指定文化財、寛文8年(1668年)に武家から寄進された将棋駒形の庚申塔がある。 碑面には青面金剛童子、天邪鬼、三猿が彫られている。 眷族の三匹猿は、「見ざる」「聞かざる」「言わざる」で、目、耳、口を両前肢で押さえている。 これは悪いことを心にふれさせないようにとの意味を表わす。 本尊の姿も悪事を打ち砕く武器を持ち悪者に向って恐ろしい顔で悪い鬼を踏まえて立っている。 |
|
|
10:36 北区の久国寺を目指していたら、普光寺へ迷い込んだ。 金色に光る大仏の背中が見えた。 そして、リズミカルなお経が山門の外まで響き渡る。 |
|
|
「北大佛」と呼ばれる高さ7.235m、全身金色の大仏。 他にこんなのも; ・どんな願いも叶えてくれる「如意輪観音」 ・自分の干支の地蔵に願うと願いを叶えてくれるという「十二支地蔵」 ドラえもんの様な寺。う〜寒っ。 |
|
|
10:40 久国寺へ到着。 慶長年間(1596年 - 1615年)に、松平家の菩提寺である法蔵寺から徳川家康の守護仏「聖観世音菩薩」を貰い受けた長国守養が楠山久国寺を創建。 寛文3年(1662年)、安祥長盛和尚が現在地に移設し、これをもって名古屋城の鬼門除けとした。 山号の天長山は、この時本丸の天長峰の名を借り改めたもの。 |
|
|
山門を潜ると、右手の楓の影に梵鐘が見えた。 当時、住職が知人から岡本太郎を紹介してもらい製作を依頼したもの。 この梵鐘は小型の試作品が5体製作され、うち1体は岡本太郎記念館に設置されている。 また、親交のあった石原慎太郎 元東京都知事にも1体贈られているそうだ。 |
|
|
お〜、岡本太郎が昭和40年(1965年)に製作した梵鐘「歓喜の鐘」。 トゲトゲで、こんな梵鐘は初めて見た。いかにも岡本太郎。梵鐘まで爆発だ! 曼陀羅をイメージして作られた。突起は、腕を突き出した人間。梵鐘の下の方には瞑想する仏様、動物、魚など森羅万象を表現。隅に「TARO」のサインがある。 |
|
|
音色にはよろこび、悲しみ、苦痛、うめき声、それが言いようのない振幅で響き渡るらしい。 突起が共鳴し複雑な余韻がいつまでも鳴り響くそうである。 普段は撞けず、除夜の鐘が唯一音を聴けるチャンス。この時は、先着108名だが一般人も撞けるそうだ。 岡本太郎は、後に梵鐘をもう一つ作っていた。それは「太陽の鐘」と言う。 直径約1.2m、高さ約2.4m。鐘を吊るす台(高さ・幅約7m)と一体の作品。現在は群馬県前橋市にある。 大阪万博Expo’70の太陽の塔と同じ顔が大きく刻まれており、岡本太郎作品と一目で分かる。 |
|
|
10:55 北警察署直ぐ北の贅食家千壽 黒川店へ到着。 うっわ〜、一方通行の出口から行列が見えた! 一瞬迷ったが、エンジンを止め、一方通行を押して行列の最後に駐輪。記帳し列に並んだ。 11:00 開店。どんどん名前が呼ばれるが、5組ほど前でストップ。2巡目を覚悟したが、何の何の。直ぐ入店。 店内は結構広く、まだまだ余裕があった。茶わん蒸しと小鉢のセットが追い付いていなかっただけか? |
|
|
オーダーは、千壽チラシ寿司ランチ1,200円。とうとうランチもこの値段になってしまったか。 色々なTV番組で紹介されており、番組に因むスペシャルメニューも多い。 美味しそうだが、ちと手が出る値段ではない。 お〜、刺身山盛り。新鮮で美味い!酢飯も美味い!これは良い! 11:23 支払いを済ませ外に出ると、行列は消えていた。なんだ、この時間に来れば並ばずに済むのか。 |
|