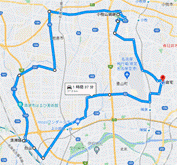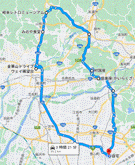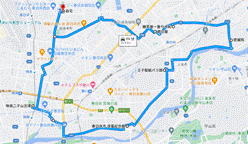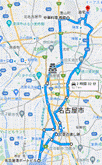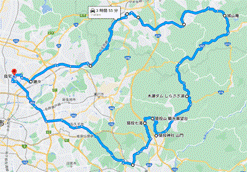|
トコトコ中国バスの旅 |
|
|
|
|
|
|||
【旅日記】
|
2022.5.6(金)
城攻め成功。駅丼ショックをカツ丼で挽回! |
|||||
|
GW 2回目のツーリングは岐阜県恵那市の岩村城。日本三大山城の一つ。石垣が素晴らしい! 途中給油必須の距離でルート選定に迷い温存していたが、岐阜城を皮切りに今年のGWは城攻めを続けて来たので思い切ってココに決めた。 その他の城は車・電車で攻略。どこも印象深い(↓)。 |
|||||
|
5/2(月) 大桑城跡 岐阜県山県市 新登山口駐車場から急峻な山道を上ること約30分。山頂の模型の城が笑える。 明智光秀の墓、モネの池なども巡る。 |
|||||
|
5/4(水) 苗木城跡 岐阜県中津川市 NAVIを信じた結果、旧北恵那鉄道上地橋梁に駐車し四十八曲りを登ることに。 Google Mapは近くのPを案内。悔しい! |
|||||
|
5/5(木) 犬山城 愛知県犬山市 10:00城下町は閑散。ところが、城は大渋滞。入場券購入に30分、登城は更に60分待ち。 登城断念。出直し。 |
|||||
|
そして、本日。 9:36 岐阜の県道66号線
東濃なんじゃもんじゃ街道沿いの道の駅 どんぶり会館でトイレ休憩。 この休憩は予定外。何せここは復路に予定していたルート上なので。 NAVIに頼り切りで道を覚えなくなった。いかん、いかん。 帰宅後、地図を見返し間違った地点を確認。標識を見た時に「もしや」と思った県道13号線がポイントだった。 次は間違えないよう注意しよう。 |
|||||
|
9:58 県道33号線
中馬かんてん街道の小里城大橋を渡った。 最大橋脚高79.5m、最大支間135m、全長420m、天空のS字橋。 遠くから見る姿は迫力があり素晴らしい。しかし、何度通ってもフワフワ感じて恐ろしい。 |
|||||
|
10:02 小里川ダムで小休止。 |
|||||
|
中々の迫力。 このダムは堰堤を通行できる。 コロナ対策で閉鎖されているが、通常は堰堤内部を見学できる。 |
|||||
|
ダムによって出来た「おりがわ湖」は貯水量が少ない。 |
|||||
|
10:30 R418の岩村城跡への入口。 久々で入口の位置を忘れてしまい緊張したが、大きくて見易い看板が出来ていた。 これなら見落としは無いだろう。 |
|||||
|
10:35 岩村城跡着。 駐車場、案内図と、良く整備されていた。 立派な観光パンフレットもあり。 隣のTriumphは量産世界最大の2458cc、超デカイ! |
|||||
|
高取城(奈良)、備中松山城(岡山)と並ぶ三大山城の一つ。 江戸諸藩の府城中、最も高い標高717mに築かれ、高低差180mの天嶮の地形を巧みに利用した要害堅固な山城。 霧の湧き易い気象までも城造りに活かし、別名は「霧ケ城」。 織田信長の叔母が城主として統治。 |
|||||
|
何度来ても、この石垣には圧倒される。 QRコードで城の再現CGや解説を提供。やるもんだねぇ。 |
|||||
|
本丸北東面の六段壁は圧巻! 今度は城下町から歩いて登ってみよう。 気持ち良さげに鯉が泳ぐ。良い時に来た。 |
|||||
|
11:15 農村景観日本一展望所へ到着。 田植えが終わり、鮮やかな緑の絨毯が広がり気持ち良い。 |
|||||
|
11:31 いわむら城下町へ到着。 全長約1.3kmの古い町並み周辺に当時の面影を残す商家や旧家、なまこ壁などが今も佇む。 NHK朝ドラ「半分、青い。」のロケ地にもなった。 人が少ない。嬉しいやら悲しいやら。 11:44 岩村駅へ。 |
|||||
|
駅舎内の「焼肉まるきん」へ“駅丼”を食べに行ったが、開店しているものの駅丼休みでガッカリ。 恵那-明智を結ぶ明知鉄道の旅も面白そう。 |
|||||
|
気を取り直して昼食を再考。 計画ルートから外れ日本大正村には寄れなくなるが、JR瑞浪駅を目指すことにした。 12:21 県道33号線を戻り、朝はスルーした道の駅
おばあちゃん市・山岡で小休止。 日本一の木製水車が回る。駐車場は満車。目的は飯だろうなぁ。ここの食堂も美味いから。 途中、カツ丼が売りの「お食事処 野内」を発見。心惹かれたが、駐車車両が多く混雑していそうなのでパス。 次回も駅丼が休みだったら、ここにしよう。 |
|||||
|
12:39 ときわ食堂へ到着。瑞浪駅から190m、昭和の駅前食堂。 あんかけカツ丼が有名な「加登屋食堂」も候補だったが、中華そばとカツ丼の評価が高いこちらを選択。 余談だが、からあげが美味かった土岐の加登屋食堂と同じ店名でも関係は無いそうだ。 とは言え、他では見掛けない店名、何か関係あるのでは? あんかけカツ丼は、卵が貴重な時代に葛を使ってボリュームを出したものだとか。次回食べてみよう。 |
|||||
|
オーダーは、迷わず中華そばとミニカツ丼のセット。910円也。 昔ながらの中華そばに、フワフワの溶き卵がタップリかかったカツ丼。美味かった! カツはヒレ肉の揚げたてでサクサク。 中華そばは+100円で大盛に。量が少ない訳ではないが、美味かったので大盛にしておけば良かった。 |
|||||
|
計画が大きく変わり、できれば避けたいR19で家路に着いた。 R21を越えた信号で白バイが横に止まり、「音が大きい」と停車を求められ「芯抜いてない?」とチェック。 交換はしたが改造はしていない。結果は「抜いてませんね。OKです」とのこと。で、音量は良かったの? ときわ食堂でカメラのスクリーンが暗い事に気付いた。少し前に出た電池切れ警告の影響と思い放っておいたが、帰宅後写真をチェックすると、いわむら城下町から暗い。カメラをチェックすると、モードダイヤルの位置がいつもと違う!横着してグローブを外さず操作した時に動かしてしまったようだ。今後は横着せず、基本を守ろう。 |
|||||
|
2022.5.8(日)
織田信長ゆかりの地を梯子 |
|||||
|
GW最終日。今年のGWは方々の城を攻めた。締め括りは、織田信長ゆかりの清州と小牧山。 最後に小牧山の麓の大八で炒飯・スープ餃子セットを食べて帰る計画だったが、途中で財布を忘れたことに気付き断念。 財布忘れ→免許証不携帯。いかんな〜。 |
|||||
|
9:24 キリンビール名古屋工場を通過。 3種類の一番搾りのテイスティングが付いた500円の有料工場見学ツアーあり。 今を去ること30数年前、この道を毎日通勤していたが一度も参加したことが無い。 是非味わってみたい。 |
|||||
|
9:30 清州城へ到着。 室町時代応永12年(1405年)、尾張国の守護職であった斯波義重が、守護所の下津城(稲沢市)の別郭として建てたのが清須城の始まりといわれている。現在の『清洲城』は平成元年に再建整備されたもの。 「清須」と「清洲」で混乱するが、歴史的に両刀使いだったそうだ。 |
|||||
|
門脇の塀は、桶狭間の戦いに大勝した織田信長が熱田神宮に奉納した信長塀のレプリカ。 弘治元年(1555年)、那古野城から織田信長入城。 永禄3年(1560年)、桶狭間の戦いに勝利。ここ清須から天下統一への第一歩を踏み出した。 |
|||||
|
10:13 小牧山の麓へ到着。 標高89.5mのこの山は木々に覆われ、近付くと天守閣が見えない。 |
|||||
|
小牧山は、昭和5年10月尾張徳川家十九代徳川義親氏が小牧市に寄贈したもの。 |
|||||
|
小牧山城は織田信長が永禄6年(1563年)に築城。 小牧市歴史館となっている現在の模擬天守閣は、名古屋市在住の実業家が寄贈したもの。 昭和42年竣工。京都・西本願寺の飛雲閣がモデルらしい。 子供の頃から慣れ親しんだ城だが、清州城と比べると隔世の感あり。 |
|||||
|
徳川義親像。歴史館まえに立つ。 歴史館からの眺めは抜群。 |
|||||
|
昼食は大八からJR勝川駅東の和ちゃんに変更。 昔ながらの、しょうゆ味のたこ焼き。 今では他に見掛けない木の船に7個入って200円! ここに来ると、何から何までタイムスリップ感が味わえる。 |
|||||
|
焼きたては中がトロトロで抜群に美味い! いつまでも続いてくれることを願う。 |
|||||
|
2022.5.14(土)
自然とクスクス笑いが出る |
|||||
|
地図を見ていて、岐阜レトロミュージアムを発見。山盛りカツ丼のみのやとセットでコースを決定。 一昨日から天気が悪く、昨夜はかなり雨が降った。 その雨も予報通り朝方止んだが、空は灰色の雲に覆われ、道路も濡れており出発見合わせ。 8:50 青空が見え始めた。道路も乾き始めたので出発。 |
|||||
|
9:44 犬山橋を渡り、岐阜県に入った。 昨夜の雨で木曽川の水量が多い。 |
|||||
|
前回スルーした鵜沼宿東の「中山道うとう峠」の石碑。 |
|||||
|
9:52 鵜沼宿。前回行われていた工事は終わり、路面がフラットで走り易い。 その分、車がビュンビュン走り危険。しかも、ここは交互通行。 そんな事で、工事はスピードブレーカー設置とそこで道路幅を狭めるものだった模様。 それよりも、先ずは一方通行にしてはどうか。 |
|||||
|
10:00 第一目的地の皆楽座へ到着。旧中山道沿いに位置する国の重要有形民俗文化財。 鵜沼宿を越えた所で、ルートと距離を確認。迷わず良かった。 津島神社の境内。鳥居の北の建物が皆楽座だが、事前調査で見た写真と違う。 と思ったら、こちらは舞台の裏側。津島神社の拝殿を兼ねており、本殿に向かう北側が正面だった。 |
|||||
|
江戸から明治時代、美濃や飛騨では、地元の人々による芝居が盛んに行なわれ、数多くの芝居小屋が建てられた。その一つ。 客席を持たない舞台のみの農村舞台ながら、廻り舞台、奈落、セリ、太夫座などを備える。 公演時は、舞台前面に蓆を敷いて見物席とし、花道は仮設で設けられた。 明治24年の濃尾地震で倒壊。明治32年に再建。現在はサークル活動、ミニコンサートなどのイベントで利用。 良く残っていた。残念ながら、内部は見えず。 |
|||||
|
皆楽座から次の目的地へ向かう途中、道端にドンガラだけのAE86が並んでいた。 廃車置き場かと思いきや、貴重な部品だった模様。 イワハラボディーワークス、中々興味深い。 |
|||||
|
10:21 第二目的地の村国座へ到着。こちらも国の重要有形民俗文化財。指定名「各務の舞台」。 村国座は、村国神社の境内にあり、元々は村国神社の奉納歌舞伎を行なう場所。 大規模な改修がされておらず、江戸~明治時代の地方の芝居小屋として貴重な存在。 場所は苧ヶ瀬池から北へ約1km。道路標識が充実しており、楽だった。 |
|||||
|
長閑な山里。 きっと、往時と変わらぬ風景なのだろう。 |
|||||
|
村国神社奉納歌舞伎は、子供歌舞伎として現在も存続。 2階建ての白壁の切妻造。小規模な芝居小屋とはいえ、廻り舞台、仮花道、太夫座、奈落を備えている。 桟敷席は1階と2階にある。劇場形式の農村舞台。 ここも内部は見えず。残念!10月第2土日に行われる奉納歌舞伎を見に行くしかない。 |
|||||
|
11:11 R418やまぼうし街道沿いの武儀川に架かる一色橋でルートチェック。 もう一つ先、山県高校前の若鮎橋を左折。順調、順調。 |
|||||
|
11:18 岐阜レトロミュージアムへ到着。 気付かず通り過ぎないか心配だったが、若鮎橋の先の山を上り、トンネルを通過、坂を下ると目の前にバシッと現れた。 入口で爺ちゃんが交通整理。オーナーかな? |
|||||
|
自然とクスクス笑いが出る。 800円/h、2,000円/3h、3,000円/日、時間制の遊び放題。 面白そうなので入ってみたいが、1時間は滞在できない。 コガネパン奥の自販機コーナーへ入ろうとしたら、料金回収のお姉さんに「有料」と言われ、ストップ。 お金の落ちる自販機コーナーは無料だと思っていたが、、、厳しいなぁ。 |
|||||
|
左ドアの奥にズラリと並ぶパチンコ台が見えた。 今度は気合を入れて来るか。 |
|||||
|
岐阜方面からR256で来る場合は、東海環状自動車道から2.8km。 「県立山県高校⇒」の標識が目印。 |
|||||
|
右折すると、右前前方に見える。 この方向からも見落とすことは先ずない。 |
|||||
|
11:37 高富郵便局近くの「みのや食堂」へ到着。計画よりも30分ほど遅れ。こちらもレトロ感たっぷり。 あ〜、外に行列。 毎年正月、近くの大龍寺に“だるま”を納めに来るが、こんな店があったとは知らなかった。 来年の昼食候補No.1。 |
|||||
|
入店まで約20分。早速カツ丼(並)をオーダー。750円の情報だったが、850円に値上がり。 豚汁320円も食べたかったが、4ケタになる。それよりも食べ切れるか心配なので先ずは様子見。 店内はコロナ感染防止で相席無しにしている様で割とゆったり。 沢山入れても調理も追い付かないだろうし。 壁には色紙や写真がいっぱい。取材も多い様子。大食いフードファイター達もいた。 |
|||||
|
来た!こっ、これは!並のご飯は450g。それだけで丼に山ができる。その上にカツが、正に山盛り。 先ずカツを丼の蓋に降ろし、ご飯に箸が届く体制作りから始まる。 正確な大きさは分からないが、間違いなくカツもデカイ。厚みも十分。 それでいて、柔らかくて美味い!待った甲斐あり! カツ丼が一番人気と聞いたが、皆さん色々食べていた。人気は焼きそばとチャーシュー麺。どれもデカイ。 猛者はチャーシュー麺の大盛とご飯大盛。どんだけ食うんや!絶対食べ切れんやろう。結末が気になる。 |
|||||
|
帰路は鶯谷トンネルを通る最短コースの計画だったが、ヘッドライトが点かないことに気付きルート変更。 金華山ドライブコースで山を越えることにしたが、昨夜の雨で落葉が滑り易い。 さらに、一方通行を逆走して来る車があり、緊張。 |
|||||
|
雨上がりで空気が澄み、気持ちが良い。 R22では側道に待機する白バイを発見。ついつい側道に出てスピードを落とし、排気音を抑える。 先日のトラウマで本能的に側道へ出たが、「とまれ」が多く面倒。直ぐに本線へ戻った。 広い国道は時間短縮出来るが、やはり好きになれない。 今度みのや食堂へ行く時には、チャーシュー麺大盛を食べよう! |
|||||
|
2022.5.21(土) 近所の史跡+α巡り |
|||||
|
予報通り朝からにわか雨。遠出はパス。 近くても濡れた路面を走るのは嫌だが、雨雲レーダーによると降っても1〜2mm。 昼食+α、近場でルート設定し思い切って出発。 先ずは、この所気になっていた八事町の「きしめん朝日屋」へ。 しかし、中々エンジンが掛からない。キックを繰り返しているうちに雨が降り出した。まいったな〜。 |
|||||
|
食べログが“掲載保留”になっており、ほぼ諦めていたが、やはり廃業していた。残念。 「あんかけ」と「志の田丼」が食べたかった! こんなこともあろうかと、バックアップに考えていたJR春日井駅近くの「麺茶屋一番や大和」へ。 11:45 到着。 店先に出ている筈のランチボードが見えず心配したが、やってる、やってる。 |
|||||
|
出発が遅れたので先客が数人。未だ誰も食べておらず、オーダーすると「少々お待ち下さい」とのこと。 オーダーは、3種類あるランチセットの中から「B. 黒毛和牛メンチカツ カレーうどん」をチョイス。 他の2種類は味噌煮込みうどんと竹天ぶっかけ・親子丼。どっちも捨て難い。どれも680円。 美味かった〜。メンチは揚げたて。カレーうどんとご飯は小振りだったが、大満足! 良い店を発見。カウンター4席、座敷に4席のテーブルが2つの小さな店。混雑するのかな? |
|||||
|
大和から出ると、雨が少し強くなっていた。進むか戻るか一瞬思案。 帰るにしても濡れるので、進ことにした。 12:28 密蔵院へ到着。小学校の遠足以来だ。 1328年(嘉暦3年)、美濃御嵩より訪れた慈妙が開創。尾張の天台仏教の中心地として栄えた小牧市の正福寺の衰退を受け、以降尾張地方に於ける天台宗の中心地(中本寺格)となった。永享末年(1441年)前後に最盛期を迎え、末寺は尾張・美濃を中心に11カ国・700ヶ所、塔頭は36坊にものぼり、七堂伽藍も備わって葉上流の伝法灌頂の道場として重きをなした。当時の学徒は3,000人を超えたとされる。 |
|||||
|
戦国時代になると織田信長が延暦寺と敵対した影響で衰退し、末寺は約100寺、塔頭も16坊となった。その後、葉上流31世の珍祐が元和元年(1615年)に密蔵院に移って七堂を再興し、さらに名古屋城三の丸に東照宮ができると別当になるなど、再建に力をふるった。葉上流の灌室を有して僧侶に位を授ける寺であるため檀家を持たず、このため明治以降は維持が困難になった。明治24年(1891年)の濃尾地震では本堂、仁王門、灌頂堂が倒壊するなどし、1932年の時点で塔頭は常泉坊のみとなった。常泉坊(現・常泉寺)は1950年春日井市内の大留町に移転し、現在に至る。 しかし、そこで墓地の案内は無いでしょう。 |
|||||
|
多宝塔。室町時代の初めに建立。国指定 重要文化財。 一重塔にひさしを付けたため二重に見える。天台宗や真言宗の寺に多い。 この多宝塔は、禅宗様式の入った珍しいもの。 屋根の軒反りや勾配がやや急で、姿は近江の石山寺を思わせるのだとか。 確かに立派。晴天なら、もっと細部が見えるだろう。また来よう。 |
|||||
|
王子製紙の赤白煙突を目指して、庄内川の堤防を西へ。 |
|||||
|
12:50 王子バラ園へ到着。 場所が分からず地図で確認しようとして、携帯電話を持っていないことに気付いた。 気付くと近所でも心細い。 |
|||||
|
こんな立派なガーデンがあるとは知らなかった。 良い時期に発見してラッキー。 |
|||||
|
12:59 小野道風誕生伝説地へ到着。 小野道風は平安時代中期の書の名人。藤原佐理、藤原行成と共に三跡と呼ばれている。 道風は、それまでの中国の硬い書風から、優雅でやわらかい日本独特の書風を新しく生み出したことで有名。 言い伝えによれば、父葛絃が尾張国春日部郡松河戸(現在の春日井市松河戸町)滞在中に、里人の娘との間に生まれ、幼少期をこの地で過ごした後10 歳頃に父とともに京に上り、12 歳で天皇に書を献上した。 全国的にも珍しい書の専門美術館「道風記念館」には、道風に関する資料や貴重な書作品を収蔵・展示。 小学生の時、小野道風展で賞を貰った事がある。当時は、こんな人物とは全く知らなかった。 今では春日井市のマスコットキャラクターになり、ナンバープレートにも描かれているので身近。 |
|||||
|
13:07 「らぁ麺 飛鶏」の前を通ったら、大行列! これはビックリ。何度も食べに来ているが、ここまでの行列は初めて。 人数を数えてみると、29人。他に車で待っている人もいるだろう。 ランキングトップ獲得を続ける大人気店。実際、とっても美味い。しかし、この行列では心が折れる。 ここで食べるためだったり、目的に加えて、遠方から来た人はそう言う訳には行かんわな。 |
|||||
|
13:12 味美二子山古墳へ到着。 春日井市で最大の規模を誇る、盾形の周溝をもった墳長94mの前方後円墳。昭和11年、国の史跡に指定。 円筒埴輪をはじめ人物・馬・家などの形象埴輪や、高坏・器台などのほか、脚付四連坏・子持蓋付脚付壺の特殊な形の須恵器が大量に出土。 出土した埴輪や須恵器などから、築造年代は6世紀前葉(約1500年前)と考えられている。 近くは良く通るが、ここに足を踏み入れたのも小学生の時以来か? |
|||||
|
エンジンを止め、跨り地面を蹴って二子山公園内の遊歩道をウロウロ。 |
|||||
|
公園内には「ハニワの館」なる建物がある。 学芸員らしき人もいた。 毎年10月に、ここで「ハニワまつり」があるのだとか。 |
|||||
|
出土した埴輪の一部を展示。 土の成分から、8kmほど離れた東山町の下原古窯跡群で作られたと推定されている。 |
|||||
|
エンジンを止めたまま、二子山公園北側の白山神社へ。 白山神社は養老元年(717)泰澄大師が加賀国(石川県)の霊峰白山(2,702m)に初登頂し、白山比咩大神(しらやまひめのおおかみ=菊理比咩命/くくりひめのみこと)の鎮座する霊峰白山を神体山として開山し、現在は全国に約3,000社の分霊社を擁す加賀国一ノ宮の白山比咩神社(しらやまひめじんじゃ/石川県白山市)が総本宮。 春日井市には4社あるそうだ。知らんかった。 ここでは、菊理比咩命・伊邪那岐命・伊邪那美命・可美真手命・天児屋根命の五柱をご祭神としてお祀り。 |
|||||
|
鳥居を潜ると、階段。 なんと、社殿は白山神社古墳の上に建てられている。 中々足が向かない近所の史跡+α巡りが出来て良かった。 が、予想以上の雨で愛車が汚れガッカリ。 ・・・ 帰宅後、速攻で洗車 |
|||||
|
2022.5.22(日) ミスコースや思わぬ休業あれど、計画完遂 |
|||||
|
つい先日、NHKの歴史探偵で「南極タロジロ物語」を見て感動。 そこで、タロとジロに会いに名古屋港へ向った。 朝は涼しく、これまでと変わらぬジャンパーで出発。 しかし、グングン気温が上がり、折り返す頃には汗だく。 来週からは装備変更だ。 |
|||||
|
9:53 宮の渡し公園へ到着。 東海道五十三次のうち41番目の宿場である宮宿。東海道にある宿場のなかでも最大級の規模を誇り、たくさんの人で栄えた。 「東海道最大の宿場・宮宿の趣を残す公園」とは、復元された常夜灯や時の鐘のこと? |
|||||
|
42番目の桑名宿には、海路を船で行く。その距離が七里であり、「七里の渡し」と呼ばれていた。 常夜灯は寛永2年、犬山城主である成瀬正房が熱田須賀浦太子堂(聖徳寺)の隣地に建立したものの、風害で破損。承応3年からは現在の位置で宮の渡しの安全を見守る役となった。しかし、火事で焼失。ほどなくして再建されたもののすぐに荒廃。昭和30年に当時とほぼ同じ位置に復元された。 そうか、犬山城と関係があったのか。 |
|||||
|
船着き場も復元されている。 |
|||||
|
時の鐘は延宝4年に尾張藩主・徳川光友の命によって作られた。熱田の住民や東海道をゆく旅人に時刻を知らせる役目を担った。江戸時代に使われていた鐘は、今も蔵福寺に保管されている。昭和58年に宮の渡し公園内に復元され、再び近隣住民や訪れた人に時間を知らせている。 と言う事だが、中は祭りの道具などの倉庫になっていた。 堀川まつりに向け、協賛者の名前入り提灯の位置を間違えないようセッティングが始まった所だった。 この分なら、今年はまきわら船の曳き回しもできるだろう。 |
|||||
|
東の新堀川には2本の橋が架かっている。 社会人になったばかりの頃、上の橋は未だ建設中だった。 下の橋を渡って大回りしなければならず、いつも面倒だと思っていたことを思い出す。 |
|||||
|
宮の渡し公園から、堀川を渡り名古屋港ガーデン埠頭に向って快調に走行。 だった筈が、R1を横断。何故? Google Mapで位置を確認。いかん、反対に曲っていた! 何十年振りかに通った道。風景では全く気付かなかった。ガッカリ。 築地口交差点を左折すると、ポートビルが見えた。 ここは車が多いと予想していたがガラガラで拍子抜け。 |
|||||
|
10:43 トラブルはあったが、無事ガーデン埠頭へ到着。 名古屋港湾会館の自転車置き場に駐車。 「戻ったら消えていた」何て事にならないよう、小走りに進む。 |
|||||
|
南極観測船ふじの主錨。 デカイ! 4,160kgもあるのだとか。 |
|||||
|
いたいた、タロとジロ。 昭和31年、第1次南極地域観測隊のソリ犬として活躍。 第2次隊の越冬中止で昭和基地に止む無く残されたが、極寒の地で1年間見事に生き抜いた。スゴイ! 彼らが生き抜けたのは、優秀なリーダー犬のお蔭だったとか。泣ける。 プロペラもふじの物。 |
|||||
|
中型雪上車SM50S。 1979年製、南極で約20年活躍。昭和基地から内陸基地へ人員・物資の輸送や内陸調査旅行に使用。 こいつはゴツイ! |
|||||
|
全長100m。デカイ! ふじは1965年(昭和40年)から18年間活躍した2代目南極観測船。本格的な砕氷艦としては日本初の船。 船内には、操縦室や医務室、乗組員のプライベート空間の居室など、当時の姿がそのまま残されている。 ヘリコプター格納庫を改装して作られた展示室「南極の博物館」では、南極の美しさ、観測の歴史や成果などを知ることができる。 300円で船内に入れるが、愛車が心配なのでパス。 |
|||||
|
クルーズ船、運行しているようだ。 中川運河を通り、金城ふ頭とささしまライブを結ぶ。 「中川口通船門」で、パナマ運河をプチ体験とか面白そう。 |
|||||
|
名港トリトンが良く見えた。 5月の爽やかな風が気持ち良い。 が、ゆっくりしてはいられない。 |
|||||
|
名古屋港シート レインランドの観覧車は回っているが、乗客0。 水族館に一番近い駐車場は満車だったが、総じて人出は少ない。今が狙い目か。 |
|||||
|
六番町からR1を東へ進み、白鳥橋を渡り、堀川東線を北上。 桜通りを横断し、最初の橋で位置を確認。 ドンピシャ、中橋。目の前に浅間神社らしき場所が見えた。 |
|||||
|
11:39 四間道 町並み保存地区へ到着。 慶長15年(1610年)に名古屋城築城と共に始まった清洲越しにともなって商人達がこの地に住み着いて作られた商人の城下町として始まり、最初の「名古屋」の街の誕生となった。元禄13年(1700年)の大火で1600軒余りが焼失し、その後尾張藩4代藩主徳川吉通は、堀川沿いにある商家の焼失を避けるために、中橋から五条橋までの道幅を4間(約7m)に拡張したのが始まり。 このことから四間道と呼ばれるようになったそうだ。 |
|||||
|
延焼を防ぐ防火壁の機能を持たせるため、尾張藩が通りの東側に石垣の上に土蔵を建てることを奨励したことから、土蔵造りの並ぶ街並みが形成されたとされている。 1945年(昭和20年)の名古屋大空襲時の那古野地区は被害が比較的少なく破壊を免れ、四間道には多くの古い町屋や土蔵など古い町並みがそのまま残った。戦後、名古屋市の都市開発などの影響で幾つかの古い町屋や土蔵は取り壊され、マンションや住宅、駐車場になった所があるものの、現在に至るまで多くの白壁の土蔵が連なり、2階に屋根神様が祀られている古い町屋も多く残っている。 |
|||||
|
元々、中橋から五条橋までの堀川の西側にある地区を指していたが、南の浅間神社から北の円頓寺商店街のアーケード入口までを1986年(昭和61年)6月10日に名古屋市が街並み保存地区に指定した。 2007年(平成19年)には那古野界隈の活性化を担って「那古野下町衆(那古衆)」が結成されたほか、2009年(平成21年)には空き家が目立っていた円頓寺商店街と四間道の那古野地区の町作りと空き家対策の活性化を目指し、那古野地区店舗開発協議会(通称ナゴノダナバンク)が発足。以後、四間道では土蔵や古い町屋が改装され、カフェやレストラン、飲み屋、雑貨屋などに利用されることが多くなったそうだ。 |
|||||
|
円頓寺商店街。エンジンを止め、押して進入。 明るく感じが良いが、人が少ない。 車に乗っていると、大須ですら行こうと思わないからな〜。 |
|||||
|
五条橋。欄干の銘板は「五條橋」。味わいのある石畳に惹かれ、昔は良く通った。 1610年(慶長15年)尾張の首府が清須から名古屋へ移転。「清須越」と言われ、翌年にかけ名古屋城築城、城下町建設資材や生活物資搬入のため堀川が開かれた。五条橋はその時架けられた「堀川七橋」の一つ。 橋の西側は東海道宮宿と中山道垂井宿を結ぶ「美濃路」。京・大阪と江戸を結ぶ重要な街道だった。 意気揚々と最終目的地の県営名古屋空港西の中華料理 鳳龍へ行ってみると、なんと開いていない! 調べてみると、日曜日は夜のみ営業。土曜休業なのでランチは無理。あぁ残念。 |
|||||
|
2022.5.28(土) 昼の営業開始前にも拘らず、待ち時間は「約180分」。こりゃダメだ! |
|||||
|
昼食を主目的にコース設定。 初めて足を踏み入れた豊田市の保見団地で道に迷いながらも計画のルートで進んだ。 ところが、、、 |
|||||
|
9:02 猿投山西回り登山道入口を発見。 展望台まで5.7km。結構距離がある。 |
|||||
|
それがこの道。 その上、偶にだが車や自転車が走って来るので気が抜けない。 |
|||||
|
まもなく広沢神社前を通過。 猿投神社の境外末社。延喜式神名帳に名前を連ねる立派な式内社。 出雲大社の祭神、大国主命と共に国を作り固めた神、少名彦命を祭神に祭る。 |
|||||
|
広沢川とクロスしながら進む。 所々に小さな滝。 |
|||||
|
木曜日の大雨で水量が多い。 やがては矢作川に流れ込み、漏水問題が発生している水源橋の明治用水頭首工取水口へ。 応急処置も中々難しい様だが、早く田んぼに水が行き渡ることを願う。 |
|||||
|
9:20 猿投七滝入口へ到着。 看板奥の遊歩道を進むと七滝。 川床が菊の花弁の様に見える球状花崗岩、国指定の天然記念物「菊石」まで150m。 車止めの柵があるそうなので、そこまでは行けそう。いざ前進。 |
|||||
|
柵はこんな感じ。 間隔が広いので通り抜けられるが、流石にここでUターン。 |
|||||
|
川には滝。 菊石は何処??? |
|||||
|
メインの道路に戻り前進。 橋が架かっている白霧滝を見物。 |
|||||
|
中々の原野感。 |
|||||
|
前半の滝も見たいなら遊歩道を歩くべし。 |
|||||
|
なるほど、こう言うことね。 猿投神社の祭神として祀られている大碓命が、猿投山で毒蛇に噛まれて傷口から流れた血を洗い流したとの伝説がある「血洗の滝」へ向う林道は通行止めのためパス。 遠くないので歩いて行ってみれば良かった。 |
|||||
|
猿投神社 西の宮。 猿投神社を本社とする西方の奥の宮。平安時代後期創建。木の葉丸という長巻(太刀)があった。 大碓命は毒蛇に噛まれたことで絶命。宮内庁管理の立派な墓所がここにある。 双子の兄弟の小碓命は、日本武尊。 |
|||||
|
ウォーキングやらランニングやら、人が多くなった。 結構な距離があり、坂もキツイ。自力では辛いな〜。 |
|||||
|
猿投神社 東の宮。 こちらは猿投神社を本社とする東方の奥の宮。同じく平安時代後期創建。 室町幕府初代将軍 足利尊氏寄進の槍と鏡があったと伝えられている。 |
|||||
|
9:48 猿投山 観光展望台の足元へ到着。 うわっ、展望台まで225段! |
|||||
|
100段までは楽勝。残り100段辺りから苦しく、休憩を挟みつつ上を目指した。 展望台が見えた時の嬉しかったこと。 |
|||||
|
豊田市を一望。 夜景が綺麗なようだが、リスクが大きい。 |
|||||
|
トロミル水車。 サバ土の入った「トロミル」というドラム缶の様なものを水車の動力で2昼夜回転させ、良質な陶磁器の原料となる石粉を作る装置。 これは復元。 |
|||||
|
10:17 猿投神社へ到着。ここは三河國三宮。 標高629mの猿投山に東の宮・西の宮を祭り、本社と合わせて猿投三社大明神と呼ばれていた。 秋の大祭には、愛知県無形民俗文化財の棒の手が奉納される。 古来より「左鎌」を奉納して祈願する習慣がある。由来は不詳だが、古老の伝によれば、双生児は一方が左利きであり、祭神・大碓命は小碓命と双生児であったので左利きであるとされ、大碓命が当地の開拓に使ったであろう左鎌が奉納されるようになったと言う。現在では、左鎌を模った板が奉納されている。 |
|||||
|
参拝者は少なく、静まり返っていた。 参道には、パワースポットのエネルギーが漲る感じがした。 |
|||||
|
天文3年(1534年) 6月22日、松平清康によって攻撃され、9つの堂塔が焼失。その後、梅坪城主の三宅氏や那須氏などが再建。 永禄4年(1561年)に織田信長が三河の高橋荘を支配下に入れると、猿投神社を保護。 明治5年(1872年)9月、近代社格制度において県社に列格し、式内社・広沢天神社などを合祀(広沢天神社は後に分祀し摂社となった)。国幣小社への昇格が内定していたが、昇格される前に第二次世界大戦終戦により社格制度が廃止された。 |
|||||
|
素晴らしい。 太鼓殿の太鼓を叩いたら、さぞかし気持ち良いだろう。 |
|||||
|
「正一位猿投大明神」 国史の初見は、『日本文徳天皇実録』の仁寿元年(851年)10月7日条、従五位下の神階を授けるという記述である。『延喜式神名帳』では「参河国賀茂郡
狭投神社」と記載され、小社に列している。また、三河国の三宮とされたという。建治元年(1175年)には最高位の正一位に達した。 最近、阿刀田高の「コーランを知っていますか」が睡眠薬代わり。イスラム・キリスト・ユダヤは唯一神云々。 その前は「神々の指紋」を読み返していた。次は日本神話を学ぼうか。 |
|||||
|
10:45 木瀬ダムへ到着。 雨のお蔭で放水が見れて良かった。 |
|||||
|
残念ながらダムの上は走れず。 |
|||||
|
ダムによって出来た「しらさぎ湖」。 緑が鮮やかで気持ちが良い。 |
|||||
|
R419とR363を結ぶ県道13号線は、カーブあり、信号無しで交通量の少ない気持ち良い道。 と、快調に走っていたが、県道353号線との分岐の先で道路工事により交互通行。 そして、その先はセンターラインが無い細い林道。 徐々に拡げて行くのだろうか? |
|||||
|
岐阜県に入り、R363から県道20号線と進むと、ついこの前通ったばかりの小里城大橋が見えた。 やはり天空の橋だ。 主目的地は、橋の直ぐ向う。 |
|||||
|
11:25 城山庵へ到着。 予想通り、駐車場にはクルマやバイクがいっぱい。 |
|||||
|
しかし、店の入口前に置かれた待合椅子には誰もいない。 これは意外と早く食べられるかも。 との、淡い期待は見事に一蹴! |
|||||
|
昼の営業開始前にも拘らず、待ち時間は「約180分」。こりゃダメだ! 先日、ぐっさん家で山盛りのからあげが紹介されていた。ぐっさんは食べ切れず、1/3ほど持ち帰り。 調べてみると、山盛りのひつまぶしを筆頭に、どのメニューもボリューム満点で大人気。 夫婦2人で切り盛りしており調理に時間が掛かるそうだ。そこにこの人気では、休む暇なく大変そう。 豚カツじゅ〜じゅ〜焼定食が食べたかったが、3時間は待てず断念。 近いうちに、平日休みを取って、かつ早目に行って必ずリベンジだ。 |
|||||
|
代わりに選んだのは、ちょっと前に Google Map で見つけた自宅近くの「スタミナラーメン
謝々」。 R19は避け、県道66号線で多治見を経由し、一気に春日井へ。 至って順調だったが、旧愛岐道路の定光寺交差点の50mほど手前で突然リアタイヤがロック! 必死にコントロールし、転倒は免れ良かった。振り返ると、路面にはS字のブラックマーク。 ガス切れによるエンストが原因?直ぐに再始動し、何も無かった様に走るが、再発しないか気が気でない。 12:54謝々へ到着。 |
|||||
|
オーダーはランチの3番、「謝々麺+ライス」 780円。 美味かった〜!ピリ辛醤油スープは、厚くスライスされた大蒜の宝探しが終るまで熱々だった。 汗だくだった私を見て、冷たいおしぼりを出してくれる気遣い。堪らない! 旧R19から一筋南。老夫婦が切り盛り。きっと旧道になる前から営業しているのだろう。 もっと早く知りたかった。次回は、ランチの2番、「炒飯ラーメン」
800円を攻めてみよう。中華飯も気になるが。 主目的は達成できなかったが、満足度はとても高い。 |
|||||