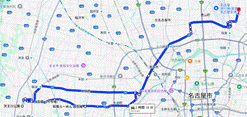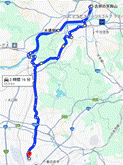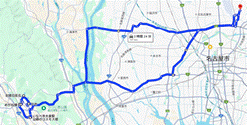|
トコトコ中国バスの旅 |
|
|
|
|
|
|||
▼My Collection -
Monkey - 訪問地 -
美食
【旅日記】
|
2025.4.5(土)
古墳と桜のチョイ旅 |
|||
|
織田信長の傅役だった平手政秀ゆかりの小牧市小木へ。 |
|||
|
10:36 宇都宮神社へ到着。 大昔、沿道を良く通った。しかし、訪問は初。何せ、古墳であり城跡であることなど全く知らなかったから。 鳥居の左辺りが『張州府志』に記載のある小木城跡。永正年間(1504~21年)に織田宰相秀雄が居城。 別名 織田宰相宅 古木城。 |
|||
|
宇都宮神社は永享元年(1429年)尾張守護代織田常昌が下野国宇都宮(栃木県宇都宮市)の二荒山神社を祀り建立したことが始まり。 小木古墳群の中に建てられた。 古墳から三角縁獣文帯三神三獣鏡が発見され、県の有形文化財に指定されている。 |
|||
|
全長59mと古墳群の中でも最大規模の前方後円墳の上に社殿が建つ。 そんな事もあり、保存状態は一番良いとか。 |
|||
|
神社西側の浄音寺古墳。 この道が古墳を避けて曲っており、相変わらず見通しが悪い。 |
|||
|
10:55 岩倉まで足を延ばし、五条川の桜をチェック。 ちょうど満開。寒気が緩み、人出も多い。 |
|||
|
先週の「愛知あたりまえワールド」の“愛知の桜の名所ランキング”では、惜しくも3位だった。 |
|||
|
この時間になると、交通規制が厳しい。 交通量も多く渋滞。 朝早く来るべきだった。 |
|||
|
毎年のことながら、桜には胸が躍る。 |
|||
|
11:05 満を持して、あの「万楽」の孫弟子が営む「麺家
中村桜」へ。時期もピッタリ。 店の前は良く通るのだが、初訪問。 殺風景な外観にボロボロの看板。本当に営業しているのか、疑問に思っていたがやっていた。 |
|||
|
オーダーは、シンプルに ら-めん大盛り 800円。 謳い文句の『鮮度抜群の国産丸骨を1本ずつ下処理し、数種類の香味野菜と一緒に時間と手間をかけて炊き上げた自慢のスープ』は、期待を裏切ること無く美味かった! 麺は中太ちぢれ。食べ応えあり。大盛りにして良かった。チャーシューは薄いが、軟らかくて味も抜群! ワンオペで頑張る孫弟子は、噂以上の愛想なし。外観に負けない殺風景な店内からも頑固さが伝わって来た。 |
|||
|
近所の公園の桜も満開。 夜、散歩に出たら、グラウンドシートに照明を持込み、花見に興じる高齢者グループがいた。 さすがに夜になると冷える。あ〜良くやるわ。 |
|||
|
2025.4.19(土)
目的は達成したが、残念な一日だった |
|||
|
先週、岐阜県各務原市の新境川堤「百十郎桜」目指して出発したものの、エンジン不調で途中で帰宅。 プラグの中心電極が融けている感じで交換。復活した。 残念ながら桜は終わってしまったので、藤の津島市へ向った。 |
|||
|
9:43 旧家が残る津島下街道を北西へ進んでいたら、見覚えのある『左 津島神社参宮道』の道標が見えた。 知った所に出て安堵。 その反面、一年前に今回の目的地前を通っていた事が分かり少々ガッカリ。 |
|||
|
9:45 津島市観光交流センターに到着。 昭和4年(1929年)に銀行建築として、柱・梁・床・壁・屋根をすべて鉄筋コンクリート造で新築。 名古屋銀行、 東海銀行津島支店を経て、 津島信用金庫本店として利用されたそうだ。 建物正面は「復興式」と呼ばれる建築様式。ルネッサンス様式を基調としながら意匠や装飾を簡略化。 ここが主目的だったが、残念なことにキッチンカー2台に前面を占拠され建物が良く見えず。残念。 |
|||
|
建物の中ではマルシェの準備中。じっくり見るのは憚られる雰囲気に負けた。 ユネスコ無形文化遺産にも登録された天王祭のまきわら舟実物大模型が飾ってある。 津島天王祭は天王川を舞台にした船祭。厳島神社の「管弦祭」と住吉大社の「住吉祭」とともに日本三大船祭の一つ。歴史は古く500年ほど前から行なわれていた。75日に亘って行われるそうだ。 主宰は津島・市江と牛頭天王社。町衆は宵祭と朝祭、市江は朝祭の車楽船行事に奉仕、神職は神事を行なう。 |
|||
|
からくり人形や屋台の模型も展示。面白い。 |
|||
|
裏には江戸時代から明治時代初期にみられる形式を持つ土蔵が残る。 明治26年(1893年)、この地に開業した津島銀行の付属家屋か、それ以前にあった商家の付属家屋と考えられている。 |
|||
|
津島市観光交流センター北の街道沿いに、花崗岩の立派な石組の「上切の井戸」があった。 津島地方は、木曽川の豊かな水がもたらす伏流水が多く、井戸には恵まれた土地だった。 古地図にはいくつかの町角に、辻井や井戸が記入されている。 これらの井戸は、通称本抜井戸と呼ばれる突抜井戸であり、湧き井戸。江戸時代、近隣住民で共同で利用。 古書には、天王祭の船や屋台の連結に使用するわら縄を編む際の打ち水に使用したとの記録がある。 |
|||
|
井戸の正面に立派なお寺「久遠山 成信坊」があった。 創建年は不詳。明徳2年(1391年)、7代慶専の時に天台宗から浄土真宗に改宗。 戦国時代に織田信長と本願寺門徒らが長島一向一揆で争った際、成信坊住職の祐念が教如上人の身代わりになり、津島御坊の称号を授けられた。 |
|||
|
江戸時代には東本願寺の門跡が東行する際に成信坊で講義をする慣わしがあった。 尾張藩の伊那備前守が成信坊で検地の公務を執り、年貢割や宗門改めも成信坊で行われるようになった。 石臼に使用されていた石が境内に敷かれていたため、俗に「ひき臼寺」とも呼ばれる。 本堂前の参道に今もその一部が残っている。 |
|||
|
境内には巨大な鬼瓦も残る。 |
|||
|
10:02 交流センター滞在が一瞬になり時間が余った。 天王川公園の藤まつりを覗いてみることにしたが、、、 |
|||
|
まだまだ。 ここも一瞬。 |
|||
|
それでも、ゴツイ機材で撮影するオッチャンあり。 |
|||
|
10:22 今市場の十王堂へ到着。 昔は死んだら冥土に行き、生前の罪業の裁判を受けると考えられていた。 その裁判を行う裁判官が閻魔大王を始めとした冥界の十王であり、十王をお祀りしているのが十王堂。 生前十王をお参りし遺族が追善法要を行うと罪を軽減されるという十王信仰が広まった。 |
|||
|
江戸時代、津島村の東西南北、今市場、橋詰、下構、北口に十王堂が建てられていた。 現存しているのは、この今市場の十王堂のみ。 北口の十王像は大龍寺、橋詰の十王像は西方寺に保存されている。下構の像は二ヶ所に分散。 |
|||
|
中央に本尊の地蔵。地蔵は地獄で変身して閻魔王になるとされている。 両脇に十人の裁判官が並ぶ。 それぞれの王の裁判の状況が赤と黒を主体に酸鼻を極めた状態で描かれたのが地獄図だそうだ。 |
|||
|
右端は変身後? |
|||
|
10:50 和風らーめん 森田屋へ到着。運送会社の駐車場にテントを構える。 3月にあちこちのTV番組で紹介され、気になっていた。 開店前の時間だが、既に受付が始まっていた。貰った赤い番号札は「8」。 トップバッターの家族は毎週来ていると話していた。 |
|||
|
トラックの荷台に紅生姜。 これは面白い! |
|||
|
出来上がると、ゴンドラで送られて来る。空飛ぶラーメン・チャーハン。 しかし、これが曲者。中々呼吸が掴み辛い。 番号札をテーブルに置いて待っていたが、商品に番号が無く案内も無いので誰のものか分からない。 おまけに、後から入って来たので後だった思った人が先に受付けていたり。 |
|||
|
オーダーは、売り切れ御免のスペシャル。叉焼麺400円とローストビーフのせやきめし400円。 ノーマルなら、らーめん300円、やきめし200円と嘘のような本当の話。 麺はインスタントに近く、チャーシュー2枚は寂しい。やきめしはべっちゃり。調理が遅いのも難点。 儲けることは考えていないそうだが、この値段でやって行くには仕方の無い事か。 帰り道、またもエンジン不調で救援車の世話になる一歩手前に陥った。IGコイルか?ポイントか?厄介だ。 |
|||
|
2025.4.27(日)
無事復活して良かったが、コンロッドにガタのある事が判明。これは気が重い |
|||
|
ポイント交換で復活!爆発圧が上がり、振動が大きくなったような気がする。 ネットで安いIGコイルを見つけたので買ってみたが、火が飛ばない!Z50A用と謳うが6V仕様ではない? 全長も短くステーも買ったのだが、、、勉強代1,500円。元に戻すと何とか走るので、バイク屋へ向った。 今回は親父さんに当たった。話をしてポイントを交換する事になったが、GWで部品の入荷は連休明け。 持込みOKだったので早矢仕へ向った。運良く買えたが、「返品不可だが日立で大丈夫か」と釘を刺された。 確認していないが、それしかないなら仕方ない。結果オーライだったが、3種類もあるのだそうだ。 無事復活して良かったが、コンロッドにガタのある事が判明。これは気が重い。 |
|||
|
試乗方々、岐阜県美濃加茂市の「古井の天狗山」へ向った。古井の読みは「こび」 10:03 天狗山へ到着。旧R41沿いで昔から良く通り、目印にもしたが初訪問。 駐車場の奥から日本一大きな12mの特大天狗が睨みを利かす。 |
|||
|
明治33年(1900年)開教の「荒薙教」と言う神道系宗教団体の本部だった。 鳥居の脇を天狗が固める。 藤棚から良い匂いがした。 |
|||
|
藤棚の奥に色付いた紅葉。どう言うこっちゃ? |
|||
|
神殿への参道も天狗が両脇を固める。 |
|||
|
祭神は、荒薙大神を主斎神として御嶽大神、白姫明神をはじめ最上稲荷、子育地蔵尊、観音様を祀る。 神出鬼没、変幻自在の天狗は大神の遣いとされる。 願い事の神様として古くから知られ、岐阜・愛知をはじめ中部一円より月参りの参拝者が多数訪れるそうだ。 胡散臭く思う私には罰が当たるかも。 |
|||
|
神殿の軒下に天狗のお面がビッシリ並んでいた。 境内の天狗は3,400体を超えるらしい。 |
|||
|
神殿内にも立派な木像。 |
|||
|
場所は飛騨川沿いの愛宕山山頂だが、眺望は望めず。 |
|||
|
こんな天狗も。 |
|||
|
この山、その昔は断崖絶壁の要衝だった。天正10年(1582年)には毛利山城、別名牛ヶ鼻砦が築かれた。 岐阜城主 織田信孝の家老、加治田城主 斎藤利堯が、兼山城主 森長可の不穏な動きに対抗して築城した。 第2駐車場に石垣が残る。 |
|||
|
10:36 加茂郡坂祝町の大連亭へ到着。いつの間にか上海亭から店名が変わっていた。 何度目の正直?漸く入店。そっけない店内は、中国の安食堂そのものでニタニタしてしまった。 メニューも値段も上海亭と同じ。何があったのか? |
|||
|
オーダーは、「中華モーニング③中国茶C」龍井緑茶。 小さな回転テーブルに蒸したての点心やお粥などが付いて、なんと500円!しかも、一日中食べられる。 お茶は薄いが大満足。その他のメニューも安い。是非また行こう。 エンジンは快調、無事帰宅。五代目食堂も健在で良かった。 |
|||
|
2025.4.30(水)
青い絨毯。素晴らしい景色 |
|||
|
ネモフィラの季節。ギリギリ間に合いそうなので三重県いなべ市の大泉駅へ向った。 秋はコスモス畑になる模様。 |
|||
|
10:33三岐鉄道北勢線大泉駅へ到着。 さて何処か?と思うと同時、踏切の向こうに青い絨毯が見えた。 間に合った。 |
|||
|
素晴らしい景色。 しかし、意外と狭い。 ここは自由に立ち入れる模様。 ちょうど電車が来た。 |
|||
|
線路沿いに北上。ねじり橋を発見しエンジンを止めて押しながら近付いていたら、電車が橋を通過。 慌ててカメラを取り出したが、変な操作をしてしまったらしくエラーが発生! そうこうするうちに、めがね橋の方へ走り去ってしまった。あ〜残念。 |
|||
|
10:56 ねじり橋の袂へ到着。 江戸時代に作られた「六把野井水」に架かる橋。 橋と用水が斜めに交差するため、アーチ橋下部のブロックは、ひねりを入れて積まれている。 この構造は「ねじりまんぽ」と言う。現存するコンクリートブロック製の橋では唯一と言われる大変貴重な橋。 |
|||
|
めがね橋と共に、平成21年(2009年)に土木学会選奨土木遺産へ認定されている。 どちらも大正5年(1916年)に竣工。100年を越える。 |
|||
|
下から見ると、捻じれ具合が良く分かる。 |
|||
|
さっきの電車を逃したのが悔しい。 |
|||
|
11:02 めがね橋へ到着。 ねじり橋から西へ230m。 |
|||
|
全国に数多く存在する眼鏡橋の中でも、大変珍しいコンクリートブロック製。 三連式のアーチが美しく、北勢線の代表的な撮影スポットとなっている。 |
|||
|
11:18 刻限日影石へ到着。 員弁町笠田新田の笠田大溜は、伊勢風土記に伊勢国の三大池の一つの野摩池であったと記されている。 寛永13年(1636年)、桑名藩主松平定綱は、灌漑用にこの大溜を改造。100haの水田を潤した。 しかし、水田の増加により用水が不足し度々水争いが起こり、死者が出るまでとなった。 弘化4年(1847年)、大泉新田里長の考案で、夕陽の当たる水路の分岐点に「刻限日影石」を建てた。 「大泉新田は日の出から7ツ半時まで、笠田新田は7ツ半時から日の出まで」と、分水時刻を石に刻入。 これで争いが無くなったと言うから素晴らしい。 |
|||
|
11:25 -大阪キッチン-おとんかつ「ひめ」へ到着。 限定20膳の日替わり定食狙いで来たが、既に開店時刻から25分経過。残っているか? と心配していたら、『本日、農作業のため”臨時休業”』。うわ〜、ヤラレタ! まさか、こんなことになるとは、、、代替案なし。さて、どうするか。 |
|||
|
11:41 多度大社東700mの鯉料理「大黒屋」で一時停止。 50m西には桔梗屋がある。時代劇の世界。どっちも悪役が思い浮かぶ。 薬効が最も高い薬用魚として、中国最古の薬物書でも紹介されている鯉。鯉こくや洗いなどが堪能できる。 多度山の泉水で育てた鯉は身が引き締まり絶品と言う。 |
|||
|
享保年間(1710~1736年)創業。 約千坪の敷地には美しい日本庭園が広がる。 |
|||
|
門の脇に”福の神、商売の神、金運の神”大黒様が鎮座。 左側は恵比寿様だったか? |
|||
|
'23年公開の映画『最後まで行く』のロケ地になった。 陰謀に巻き込まれていく刑事とそれを追う監察官の追跡劇。 鯉がいる池と古いコレクション倉庫があると言う設定で、仙葉組・組長の自宅として撮影に使われた。 帰路、ことぶき飯店佳子に寄る事を考えたが、パス。昼飯抜きになってしまった。 |
|||