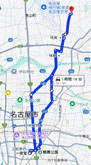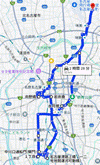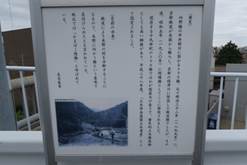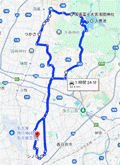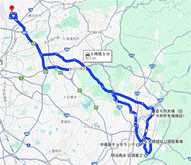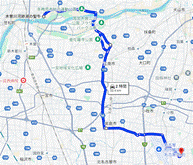|
トコトコ中国バスの旅 |
|
|
|
|
|
|||
▼My Collection -
Monkey - 訪問地 -
美食
【旅日記】
|
2025.5.4(日)
何気なく通過していた橋を見上げてみれば |
|||
|
土木学会選奨土木遺産続きで、犬山市の彩雲橋へ向った。 GSでエネキーを忘れたことに気付き、現金で給油。350円投入し、2.04ℓ。172円/ℓ、高い! |
|||
|
10:58 犬山橋へ到着。道路橋と鉄道橋が並行していることから「ツインブリッジ」と呼ばれる。 橋の中央に設けられたバルコニーは、木曽川と犬山城の絶景スポット。 以前は鉄道道路併用橋だった。あの頃は、いつも渋滞で苦労した。 |
|||
|
鉄道橋は、橋長223.15 m、支間長73.15 m、幅員16 m、3径間鋼下路曲弦ワーレントラス橋。 大正14年(1925年)に建設され、翌年から鉄道の運行が開始された。 昨年9月、こちらも土木学会選奨土木遺産に認定された。 |
|||
|
天守に大勢の人。さすが、観光のベストシーズン。 犬山城下の分岐を右へ進むと目の前が彩雲橋。 昭和4年(1929年) 竣工。令和3年(2021年)土木遺産認定。 昭和初期の犬山城附近の観光開発の中で木曽川へ流れ込む郷瀬川上に架けられた鉄道レールを用いた瀟洒な2連アーチ橋。 |
|||
|
昭和2年、昭和天皇来訪時に休息処として建てられた洋館「彩雲閣」に因む。 主部材にアメリカ・カーネギー社製造鉄道レール用鋼材を使用。名鉄の古レール。 |
|||
|
日本ラインと名付けられたこの辺りは、中生代に海底で堆積してできた硬い岩盤のチャート。その上にアーチが組まれている。 郷瀬川から木曽川へ流落する滝も絶景。 |
|||
|
彩雲橋を渡ると城下トンネルが現れる。 明治45年(1912年)、名古屋市上水道施設の整備に伴い、木曽川から取水する水門と取水場を結ぶ管理通路として掘られた。 岩盤面が露出した味わいのある手掘りトンネルだったが、令和4年(2022年)に内部の岩盤剥落を機に調査し危険個所が多数見つかりコンクリートで覆われた。景観としては残念。 |
|||
|
城下トンネルの西に、給水開始50周年を感謝した名古屋市長名の碑が建つ。 「名古屋市民の生命の水」と刻まれている。 |
|||
|
11:47 楽田駅西の「つかさ」へ到着。 うわっ、ランチ休み。2連敗。 「チキンかつ定食」か「うな丼」か、決め切れず来たがガッカリ。 近いうちにリベンジだ。 |
|||
|
上街道を南下。 楽田城
北之門旧跡。往時を思わせる痕跡は無い。 更に600m南下し、旧R41への合流地点の鳥社天神社が南門と言うから広かったんだ。 その先の中華料理店は何度か行ったことがある。隣のペルー料理店のローストチキンは一度食べてみたい。 |
|||
|
レンゲ畑が広がっていた。時折風に揺れる姿が美しい。 レンゲは元々水田の緑肥として栽培されて来た。 現在では野生化し水田や周辺の畦、休耕田、草地などに見られる。 休耕田か?コメ不足の今、ならば何とも勿体無い。 |
|||
|
帰宅し昼食。 人生餃子の皿台湾。美味かった〜。 多少手間はかかるが、あの大行列に並ばずして食べられるのは有り難い。 しかし、店でトッピングのチャーシューを載せて食べてみたい。 |
|||
|
2025.5.11(日)
斜めに走るJR中央線に惑わされて迷子になった |
|||
|
食べログで偶然見つけた名古屋市中区の一夜堂がメチャクチャ気になった。 近くのスポットと言えば鶴舞公園。 イベントを調べてみたら、バラが見頃とのことで行ってみることにした。 |
|||
|
11:25 鶴舞公園へ到着。何十年振りだろう? 鶴舞公園は、明治42年(1909年)に名古屋市が設置した最初の公園。 コロナ禍が明けて出社するようになり、通勤の電車から変貌した姿を見て気になっていた。 |
|||
|
公園中央の噴水塔。 明治43年(1910年)、第10回関西府県連合共進会に合わせて建設された。 設計は夏目漱石の義弟、鈴木禎次。 ローマ様式の列柱はドリス式。水を最上部まで揚げ、8本の突起部から自然に落水させている。 |
|||
|
見事に咲いていた。 約120種1,400本のバラが、春と秋に見ごろを迎えるそうだ。 |
|||
|
まもなく約2万株の花菖蒲が見頃になる。 |
|||
|
屋台が立ち並び賑やかだった。 正面の奏楽堂付近に踊る集団を発見。別の国へ迷い込んだよう。 奏楽堂は、噴水塔と共に建設されたルネッサンス風円形舞台。設計は同じく鈴木禎次。 ドーム型の屋根を備え、手すりには君が代の楽譜が象られている。昭和9年(1934年)の室戸台風により崩壊し平らな屋根を備えた2代目が造られたが、平成9年(1997年)に初代奏楽堂を復元。 |
|||
|
アーミーキャットの散歩。 昨日、TV番組でそんな姿を見て、「本当にそんな人がいるんかい?」と思っていたら、いたので吃驚。 |
|||
|
11:57 一夜堂へ到着。 簡単に行けると思ったが、斜めに走るJR中央線に惑わされて迷子になり苦労した。 店の前に若者が1人。スマホを弄っていたので待っていると思ったが、近付くと立ち去って行った。 自宅前駐車場に建てたのであろう店に入ると、カウンターのみの7席は満席。どう見ても常連さんばかり。 |
|||
|
オーダーは、一夜堂中華そば・大盛り・ご飯。合わせて800円! どうやら、開店した’92年から価格据え置きの模様。頑張るな〜。 先ずスープ。一口飲んで懐かしさを感じた。そうだ、近所にあったラーメン屋とソックリ。嬉しい。 葱の下に焼豚が何枚あったのだろう?美味かった〜。 少々遠いが、病み付きになりそう。 |
|||
|
2025.5.31(土)
名古屋橋巡り |
|||
|
この所、週末になると雨が振る。 数日前の天気予報では今週も雨模様だったが、どうやら午前中は持ち堪える予報に変わったので出発。 今回は、名古屋市の土木学会推薦土木遺産の橋を巡ってみた。 |
|||
|
10:12 中村区の向野橋(こうやばし)へ到着。 JR東海名古屋車両区等を跨ぐ跨線橋。「向野跨線橋」、「向野跨線道路橋」、「かまぼこ陸橋」とも呼ばれる。 かつては道路橋であったが、橋の老朽化に伴い、2002年に歩行者専用となった。 原動機付自転車は通行可。エンジンを止め、押してスロープを上る。 |
|||
|
スロープに並行して近鉄名古屋線が走る。 |
|||
|
JR東海名古屋車両区への引き込み線部部分に、長さ119m、幅5.5mのトラス橋が架かっている。 昭和5年(1930年)、当時の日本国有鉄道名古屋機関区設置時に設けられた。 |
|||
|
トラス橋部分は、明治32年(1899年)、京都鉄道によって保津川橋梁として京都の保津川に架橋されたもの。 米国A&Pロバーツ社製。 当時は日本最長であった支間長は、保津川下りに配慮したものであったと言う。 大正11年(1922年)、保津川橋梁で列車の脱線転覆事故が発生。損傷を受けた際の修理跡が今も残る。 |
|||
|
名古屋駅まで直線距離で1.35km。 南側には、JR関西本線、あおなみ線が走っている。 風景を眺めていたら、雨が振って来た。マズイ。 この後、雨宿りを繰り返しながら前進。 |
|||
|
10:35 堀川を境にした中村、中川、中の3区を繋ぐ岩井橋へ到着。 大正12年(1923年)竣工。現存する鋼アーチ桁橋では日本で2番目に古い。 大正8年(1919年)、名古屋市が5大幹線道路の建設を開始。第1号線として岩井町線を計画。 4年後、鶴舞公園から西に延びる名古屋市道岩井町線が堀川を越える場所に岩井橋が竣工。 |
|||
|
四隅に設けられた荷揚げ用の階段を下りて接近。 設計は日本橋梁株式会社技師長の関場茂樹、施工は日本橋梁株式会社。 建築家の武田五一も意匠の設計に関与。 武田五一は同じく岩井町線が新堀川を越える場所の記念橋も設計。 |
|||
|
鉄の供給事情が逼迫していた時代だったが、破格の43万1000円という工費が投じられた。 平成11年(1999年)に床板改修工事が実施されたが、竣工の橋が架け替えられることなく今日に至っている。 長さ30m、幅29.5mの斜橋形式鋼製アーチ橋が6車線を支える。 |
|||
|
11:05 港区の港橋へ到着。 1号地埋立地と2号地埋立地との連絡橋として、明治39年(1906年)竣工。 目の前に名古屋港ポートビルが見える。 東を向いたら次の目的地。と思いきや、、、 |
|||
|
公園が広がっていた。 港橋は、老朽化により、昭和11年(1936年)に現在の永久橋となったそうである。 |
|||
|
旧1・2号地間運河に架かる稲荷橋まで行くと、目的の名古屋港跳上橋が見えた。 |
|||
|
堀川河口部の西側に位置し、昭和2年(1927年)から昭和55年(1980年)まで運行。 東海道本線の貨物支線、通称「名古屋港線」。旧1・2号地間運河可動橋、堀川可動橋とも称する。 日本では現存する最古の跳上橋。可動橋第一人者の山本卯太郎が設計。 4連の桁により構成され、そのうち1径間が可動桁で上部カウンターウエイト式。 |
|||
|
カウンターウエイト頂部は鉄骨アームを介して鉄柱に連結され、可動桁が昇降しても、そのカウンターウエイトは常に直立するように装着されている。 電動機の回転は、小歯車を経て、可動桁支点部にある大歯車に伝えられ、可動桁を昇降させる仕組み。 隅田川駅跳上橋(東京都荒川区)等と同じメカニズムにより可動桁を昇降させる。 |
|||
|
線路はコンクリートの堤防で封鎖され、跡形もない。 |
|||
|
それでも国の登録有形文化財であり、壊すに壊せないか。 |
|||
|
ガーデンふ頭を横切り、中川運河に架かる中川橋へ向かった。 ところが、中々近付けない。 行ったり来たりを繰り返し、結局住宅街を抜けて金城ふ頭線を進むことに。 |
|||
|
11:37 中川橋を渡り右岸へ到着。 またも堤防に登らなければならないか、、、 |
|||
|
と思ったら、回り込むことができた。 第二次世界大戦前の昭和5年(1930年)に中川運河開通と同時に架橋。 重量600tの鋼製下路式ブレースドリブタイドアーチ形式橋梁。 大阪鉄工所(現在の日立造船)が施工。 |
|||
|
名古屋市内では珍しい形式の橋梁。これほど古い橋は国内でも現存数が少なく貴重。 大正時代に内務省が制定した「道路構造に関する細則案」に基づき設計されたもの。 寸法単位がフィート・インチでリベット接合されているなど、当時の設計思想や技術がそのまま残る。 昭和46年(1971年)に名古屋市電築港線が廃止されるまでは、路面電車が橋上を走行していた。 |
|||
|
会社には行ったばかりの頃、良く通ったことを思い出す。 カメラ用の三脚が幾つも並んでいたが、特別な日だったのか? |
|||
|
11:44 中川口通船門(閘門)へ到着。R23の真下。 水位差のある名古屋港と中川運河を船で通航できるよう、昭和5年(1930年)に第一閘門が整備された。 最盛期には、10時間以上の待合を強いられたことから、昭和38年(1963年)に第二閘門を増設。 利用の減少により平成3年(1991年)に第一閘門は閉鎖。第二閘門は現在でも使用されている。 |
|||
|
中川橋から400m。 ここにも三脚が並んでいた。 |
|||
|
緑の管理センターが目印。 |
|||
|
構造は、観音開きの水門を有するマイターゲート式。 名古屋港は潮の干満により水位が基準面+0.0mから+2.6m変化する。 中川運河の水位は名古屋港基準面+0.2mから+0.4mとほぼ一定保たれ、通常、運河の水位が低い。 通船門は、水門で仕切られた閘室内の水位を上下に調節することにより船の通航を可能にしている。 |
|||
|
12:25 中区の水月楼へ到着。 東別院のマンションが立ち並ぶ住宅街に、昭和然とした佇まいの激安中華のお店。 正午を過ぎ、混雑を心配したが、先客1名で店内はガランとしており拍子抜け。 |
|||
|
オーダーはカイコウ飯450円とラーメン300円。2品頼むと50円引きになり、支払いは700円。安い! ボリューム満点で味もバッチリ。小粒の唐揚げも美味い! 私の次にオーダーした人は、残念、売り切れ。 その次に来たタクシードライバーもオーダーしていたから人気度が分かる。 |
|||
|
ラーメンも十分美味かった。スガキヤのラーメンが430円になったこの時代に、300円とは驚き! 爺ちゃんがワンオペで奮闘。しかし、熟練の技で手際が良い。これにも驚き。 更に、会計がセルフ。レジ台に100円玉を山積みにして、性善説でキャッシュを動かしているから凄い! 良い経験をした。 |
|||
|
2025.6.7(土) 自衛隊のT-4練習機墜落から3週間少々 |
|||
|
予定していた食堂の閉店が分かり、ガッカリして出掛ける気が失せ読書に耽る。 昼が近付き、漸く出発。 行先は、犬山。入鹿池の状況が気になっていた。 |
|||
|
11:11 犬山市の入鹿池へ到着。あれっ、未だ通行止め。 5月14日、ここに自衛隊のT-4練習機が墜落した。離陸から僅か数分後の出来事だった。 何十年も前になるが、上空で黒煙を上げ錐揉み状態になった自衛隊機を目撃した。 子供心に恐ろしかったことを思い出した。 |
|||
|
池に捜索の影は見当たらず。 未だエンジンが見つかっていないと聞く。早く見つけ全容を解明して欲しい。 それにしても、湖畔の茶屋は営業できず大変。普段ならボートの稼ぎ時だろうに。 |
|||
|
11:27 尾張冨士大宮浅間神社へ到着。 明治村の前を通り、すれ違いできず渋滞したクルマ達を横目に走り抜けて来た。 濃尾平野を見下ろす尾張の富士山に鎮座。 ご祭神は、木花開耶姫命。子供の守護神であることから「子預け発祥の神社(やしろ)」と呼ばれている。 |
|||
|
5月5日に「預け子祭」が行われ、人々は虫封じや学業向上、そして安産、子授けなどを願う。 背くらべ伝説による「天下の奇祭 石上げ祭」が毎年8月第一日曜日に行われる。 大勢が力を合わせて石を運び上げ、家内安全や五穀豊穣を願う。 この辺りは奇祭だらけ。 |
|||
|
結構急な坂。 見ただけでゾッとして帰って来た。 何度か上ったことがあるのだが、、、 |
|||
|
12:20 近所のシノワへ到着。 ほぼ毎週通っている店。 計画は楽田の「つかさ」のチキンかつ定食だったが、またも営業しておらず。残念。 |
|||
|
オーダーは、ランチセットF 「チャーハン+タンタンメン」 1,000円。4月初めに100円upしてこの値段。 抜群に美味い!担々麺は卵とじ。炒飯はパラパラ。どちらも堂々の一人前のボリューム。 A〜Fまであるランチセットはどれを食べても美味くて量も満足だが、Fの対抗は Bの「中華板+ラーメン」。 ここの中華板は兎に角絶品!FとBを繰り返す日々はこれからも続くことだろう。 |
|||
|
2025.6.21(土) 昔の人の知恵とパワーは凄い |
|||
|
今週は暑かった。6月にも拘らず37℃に迫る勢い。どうなっちまうんだ? 幸いにして幾分下がったので出掛けることにした。 目的地は、豊田市の土木学会選奨土木遺産、百々貯木場等々。 |
|||
|
10:03 豊田市の百々貯木場へ到着。 矢作川の中流・左岸に位置する水中貯木場。地元の材木商・今井善六が造営。大正7年(1918年)竣工。 河川の中流域に位置する貯木場は全国的にも珍しく、木材流送等、河川が交通に使われていた。 明治~大正期に特徴的な人造石工法を用いた大規模な構造物であり貴重な遺産。 |
|||
|
貯水池、樋門、堰堤、足場用小提、引揚スロープ、製材所跡などの主要な施設が残っている。 明治以前から長野県、岐阜県の林産物輸送は、矢作川、巴川の水運が利用されていた。 当時は、筏に組まず、材木に刻印を押して所有を明らかにして目的地まで1本ずつ流す「管流し」だった。 しかし、出水時などに、木材が他人のものと交じり合って所有権を争ったり下流に流れる問題があった。 その対策として、流してきた木材の置き場として貯木場を考え、愛知県知事に建設許可を得て建設したもの。 |
|||
|
10:27 矢作川に架かる水源橋へ到着。おっ、通行止め。ここを渡る計画だったのだが。 ここは昭和33年(1958年)竣工の明治用水新頭首工。三代目。初代は約1,200m上流に造られた。 三代目は右岸から左岸へ一方通行で車も走れた。しかし、狭くて神経を使うので好きではなかった。 二代目が農業用水史上初期の横断堰堤。服部長七考案の人造石による大規模な堰堤で唯一現存。 水田に適さず不毛の地と言われた西三河の碧海台地が、この用水により美田に生まれ変わった。 大正時代には、安城市が「日本のデンマーク」と称して教科書に掲載されるほど画期的な成功を収めた。 |
|||
|
明治用水は五つの幹線水路からなり、安城市を中心に8市を潤し、工業用にも利用されている。 その頭首工の左岸で、2022年(令和4年)に大規模な漏水が発生。 数か月に亘り農業用水などの取水が制限されるなどの影響が広がった。 老朽化などにより、水が取水設備の下を通り抜けたことが原因。 土台部分をコンクリートにした上で、水門の柱を建て直す工事が進められている。完成は2027年予定。 |
|||
|
左岸と言えば、県道との交差点の信号で停車する場所。それが根元なのだろう。 その左岸の上流200mに、明治41年(1909年)竣工の旧頭首工跡が残る。 堰堤は中央部に筏通し、左右に夫々放水門2門、排砂門5門を備えていた。 明治39年(1906年)に船通し、大正6年(1917年)に魚道が増築された。 態々右岸に回ったが、こんなことなら素直に左岸へ行くべきだった。 |
|||
|
10:45 鵜の首橋へ到着。 矢作川の鵜の首狭窄部と呼ばれる川幅が狭まっている部分に架けられている。 緑の中に鮮やかな朱色の橋が見えた。 |
|||
|
う〜ん、この橋も狭い。が、交通量が多い。 この狭さで対面通行なので、対向車の無い事を確認して進入。 昭和38年(1963年)竣工。山の中であり、当時は必要十分だったのだろう。 |
|||
|
鵜の首橋を左岸へ渡ると、丸根城跡への登城口があった。 120m先に城跡。 地図をチェックすると、反対側にPあり。移動。 |
|||
|
登城口からは紫陽花ロードだった。 |
|||
|
Pを越え、城跡ギリギリの日陰へ駐輪。 目の前が虎口。 その奥に北曲輪。 |
|||
|
深い空堀が残っている。 |
|||
|
城主及び築城年代は確実な資料が無く不明。 「東照軍鑑」に、永禄4年(1561年)に「丸根ノ城」の記事が記載されているが決定的な資料が無い。 |
|||
|
主郭。ここから矢作川に睨みを利かせていたのだろう。 何せ、一番狭い鵜の口が見下ろせる絶好の場所なのだから。 |
|||
|
内環状線からの鵜の口橋の眺めは絶景! |
|||
|
11:05 中毒飯 チョモランマへ到着。派手な看板でアピール。 計画していた食堂の閉店が分かり、あれこれ探していて発見。 決定打は、このコメ不足の時にも同じ値段で3サイズ選べること。 開店5分で、30席の8割が埋まっていた。 |
|||
|
オーダーは、チャーシューエッグ定食 930円。ご飯は特盛440g。平日なら、+50円で唐揚げが1つ付く。 もやし炒めの上に厚さ1cmを越えるチャーシュー。その上に目玉焼きが載る。ご飯は山盛り。並盛の2倍。 このご飯の量なら、チャーシューは1枚で十分。美味かった〜!豚汁もバッチリ。 難点は、ご飯の質。今は仕方がない。米騒動が終ったら、美味くなることを期待。 チャーシューエッグが売りと思っていたが、6:4ぐらいで唐揚げが多かった。気になるなぁ。 |
|||
|
2025.6.28(土) 河畔から随分離れた所にあった |
|||
|
土木学会選奨土木遺産続きで岐阜県羽島郡笠松町のトンボ池の「木曽川河跡湖の聖牛」へ向った。 本日の予想最高気温は35℃。出発早々から背中が焼ける様に熱い。 暫く夏休みに入るかなぁ。 |
|||
|
10:25 トンボ池へ到着。 周囲をぐるっと一周回ったが、目的の聖牛は見当たらず。歩いて探すことにした。 どうやら、500m先に在る模様。 |
|||
|
色褪せた看板の足に土木学会の認定プレートが取り付けてあった。 選奨理由は、水制工の構造や設置状況が往事の姿のまま詳細に観察でき、治水技術が理解できること。 『聖牛』とは、川の流れを変化させるための水制の一種。 治水に力を入れた武田信玄の時代に生まれ、江戸時代に発達。 |
|||
|
太い丸太を三角錐の形に組んで川に設置されたもの。 増水時に流されてきた土砂を岸側に堆積させることで、川岸を守る働きをする。 |
|||
|
池の畔まで行ってみたが、雑草が生い茂り良く見えない。 |
|||
|
冬場は石積みの土台まで見えるばかりか、そこまで行けるかも知れない。 少々残念。 |
|||
|
河畔から随分離れている。現在の木曽川河畔は、最も近い所でも130m先。 聖牛の竣工は大正13年(1924年)。往時はこの場所に激流が押し寄せて来ていたのだろう。 上流側の遠くにハイウェイオアシスの観覧車が見えるが、川の真っ只中だったに違いない。 |
|||
|
11:03 川島大橋へ様子を見に行ってみた。 令和3年5月(2021年)の豪雨により、4橋脚のうちの1本に傾斜する被害が発生し通行止め。 昨年は通行止めになっていることを忘れ、この橋を渡ってアクア・トトぎふへ行こうとして往生した。 復旧工事の完成は、2026年〜28年。まだ暫く不便が続く。 |
|||
|
川島大橋の北100mの所に廃車置き場があった。 旧車、しかも外車が多く、面白い。 |
|||
|
クルマとしては生涯を終えているが、楽しませてくれる。 |
|||
|
11:25 愛知県に戻り、江南市の大豊へ到着。 岐阜県側で探したが、目ぼしい店を見つけられなかった。 見つけたのは老夫婦が営む昭和レトロなこのお店。 |
|||
|
オーダーは、あんかけ400円とかつ丼600円。 どちらも懐かしい味。きっと、昔から何一つ変わっていないのだろう。 「良かったらどうぞ」と、自家製の梅干しを出してくれた。そんな気遣いも嬉しかった。 帰り道、Book-off 2店へ寄った。どちらの店でも探していた本を発見。ラッキー。 |
|||